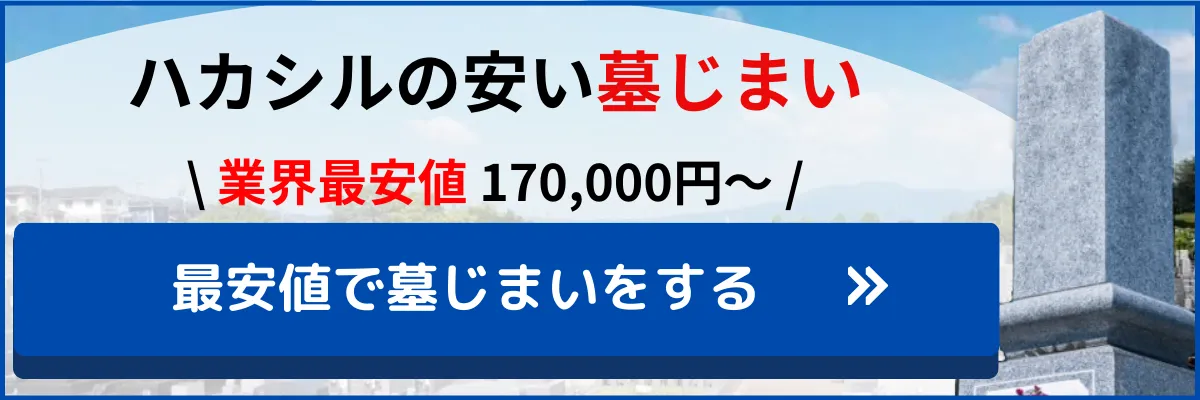墓地を譲渡するとき前に知るべき手続きと注意点
墓地の譲渡が原則的に認められていない理由や、譲渡できるケース、また、お墓の引き継ぎ先が決まらない場合に知っておきたいことについても詳しく説明しています。
墓地の所有者であれば、今後のことを考える上で、この記事を読むことで、墓地を譲渡する際に必要な手続きや、トラブルを避けるために押さえておくべきポイントが理解できるでしょう。
墓地の譲渡が原則としてできない理由
譲渡禁止特約とは、契約書に「第三者への譲渡を禁止する」という条項が付されることであり、契約上の地位の移転や債権・債務の譲渡・担保への提供を禁止するものです。
墓地の契約をする際にも、第三者への譲渡を禁止することが多く、これを譲渡禁止特約と呼びます。
墓地に関する特約については、永代使用権の譲渡・貸与ができないことや、墓地の所有者である寺院・霊園の許可を得ずに無断で他人に売る、プレゼントする行為は禁じられています。
お墓を譲渡できるケース
譲渡禁止特約が設けられていない場合、譲渡禁止特約が設けられているけど、事情があって管理者と話し合いの上、許可してもらえた場合はお墓を譲渡できます。ただ、売却・譲渡を許してもらえる確率は低いため注意が必要です。
お墓を譲渡することは可能であり、民法555条により売買契約の対象となっています。また、民法466条1項により、債権が譲渡可能であることが明示されています。
お墓の所有権は永代使用権であり、一定期間が経過すると消滅するため、要らなくなったお墓を譲渡する場合があります。相続人以外でも許可を取ることができたら、お墓の承継が可能であるため、所有者の死亡後にお墓を譲渡することができます。
お墓の引き継ぎ先が決まらない場合に知っておきたいこと
まずは、親族や地域の慣習に従って、話し合いで決めることができます。昔ながらの習慣では、長男が引き継ぐことが一般的でしたが、最近では少子化の影響で、長男以外の子どもや甥、姪が引き継ぐこともあるようです。
また、お墓の管理を霊園や寺院に依頼する永代供養付きのお墓に移動することもできます。永代供養とは、遺族の代わりに遺骨の管理を行うことで、お墓の管理を心配する必要がなくなります。
さらに、祭祀承継者となるための資格に制限がないため、相続人や親族でなくても他人を祭祀承継者とすることができます。
しかし、お墓の所有者が亡くなってから、誰が引き継ぐか意見がまとまらずトラブルになることがあるため、あらかじめ話し合っておくことが大切です。また、自分でお墓を持たず、供養の仕方を選択する人も増えています。
お墓の引き継ぎ先が決まらない場合には、慎重に選択し、話し合いを大切にすることが重要です。
墓地の譲渡についてよくある質問
墓地を譲渡することができない理由は
契約上の地位の移転や債権・債務の譲渡・担保への提供を禁止する譲渡禁止特約が契約書に書かれているからです。
どのようなケースでお墓を譲渡することができるのか
譲渡禁止特約が設けられていない場合、譲渡禁止特約が設けられているけど、事情があって管理者と話し合いの上、許可してもらえた場合はお墓を譲渡できます。
お墓の引き継ぎ先が決まらない場合にどのような対処法があるのか
まずは、親族や地域の慣習に従って、話し合いで決めることができます。昔ながらの習慣では、長男が引き継ぐことが一般的でしたが、最近では少子化の影響で、長男以外の子どもや甥、姪が引き継ぐこともあるようです。