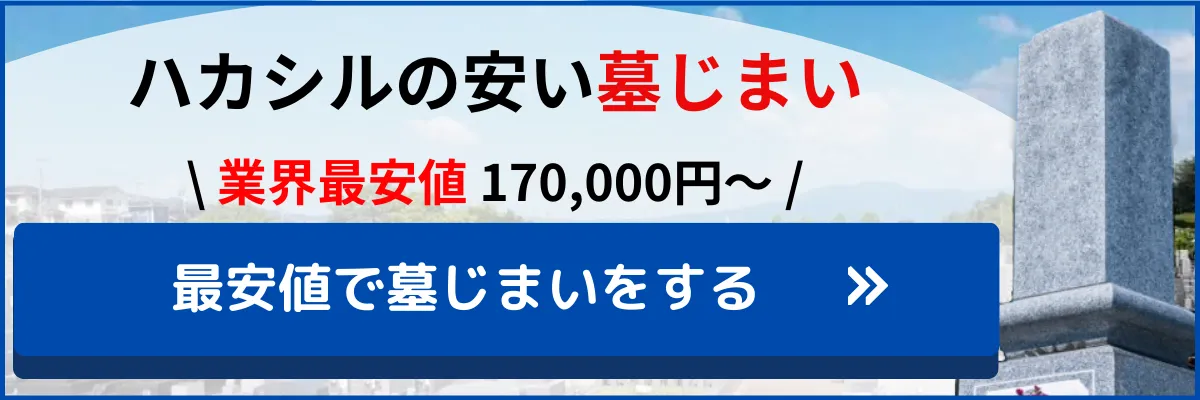жЁ№жңЁи‘¬гҒ®ж„Ҹе‘ігӮ„д»•зө„гҒҝгғ»йңҠең’гҒ«зҙҚйӘЁгҒҷгӮӢжі•иҰҒгҒ®жөҒгӮҢгҒЁжңҚиЈ…гӮ„гғһгғҠгғј
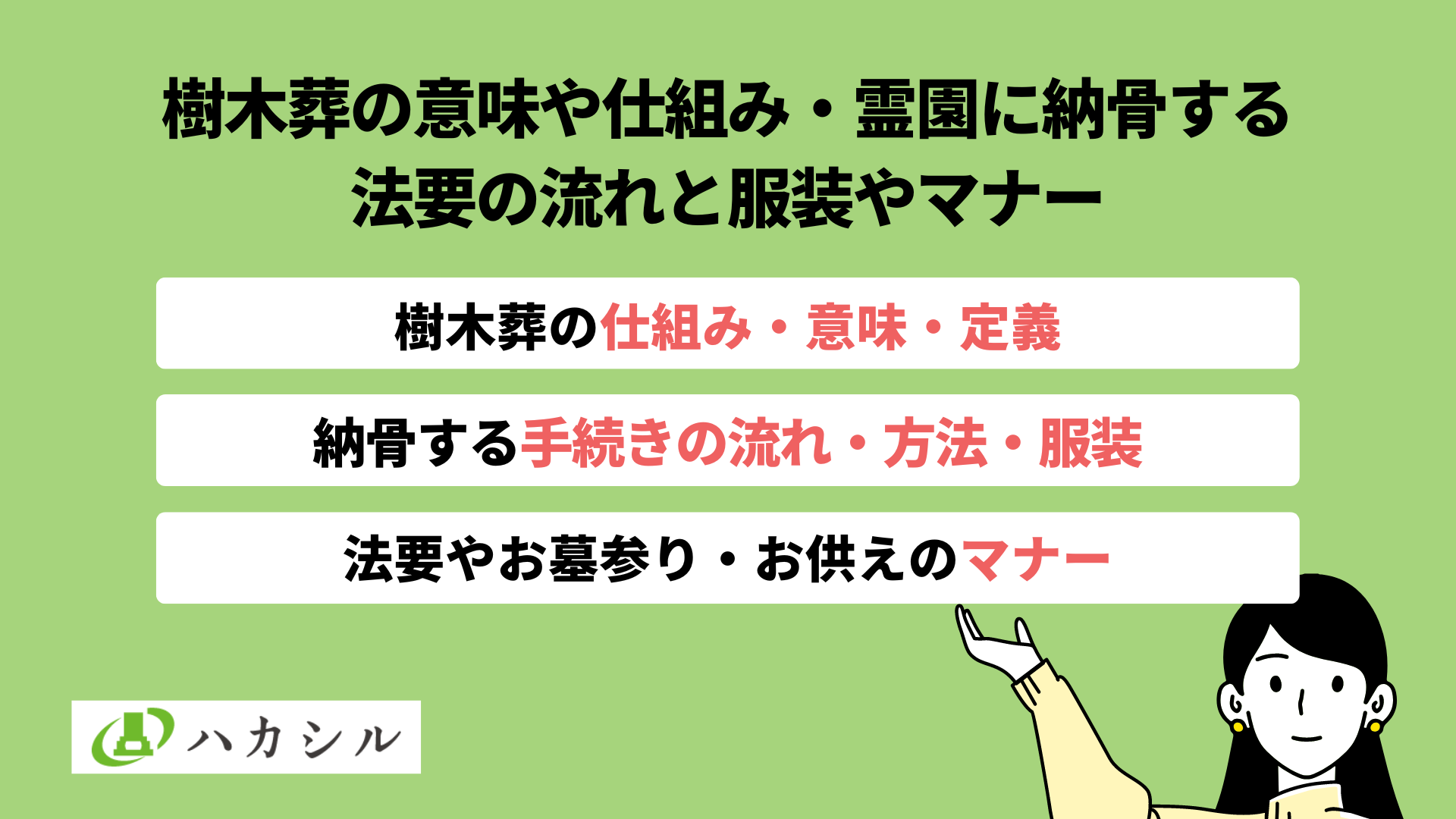
пҪўCMгӮ„гғҒгғ©гӮ·гҒ§гӮҲгҒҸиҒһгҒҸжЁ№жңЁи‘¬гҒЈгҒҰгҒӘгҒ«пјҹпҪЈ
пҪўжЁ№жңЁи‘¬гҒ®зҙҚйӘЁгҒҜгҒ©гӮ“гҒӘд»•зө„гҒҝпјҹпҪЈ
гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒҢеӨҡгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жЁ№жңЁи‘¬(гҒҳгӮ…гӮӮгҒҸгҒқгҒҶ)гҒҜгҖҒеў“зҹігҒ®д»ЈгӮҸгӮҠгҒ«жЁ№жңЁгӮ„гҒҠиҠұгӮ’еў“жЁҷгҒЁгҒ—гҒҰж•…дәәгӮ’дҫӣйӨҠгҒҷгӮӢзҙҚйӘЁе…ҲгҒ§гҒҷгҖӮжүҝз¶ҷиҖ…гҒҢгҒ„гӮүгҒӘгҒ„гҖҒе№ҙй–“з®ЎзҗҶиІ»з”ЁгҒҢгҒӢгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҖҒиҮӘ然гҒ«йӮ„гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§дәәж°—гҒ§гҒҷгҖӮ
жЁ№жңЁи‘¬гҒҜеұӢеӨ–гҒ«зҙҚйӘЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ§гҖҒеұӢеҶ…гҒ«зҙҚйӘЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гӮ„зҙҚйӘЁе ӮгҒЁжҳҺзўәгҒӘгҒЎгҒҢгҒ„гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮжЁ№жңЁи‘¬гҒ®ж„Ҹе‘ігӮ„д»•зө„гҒҝгӮ’зҹҘгҒЈгҒҰгҒҠгҒӢгҒӘгҒ„гҒЁгҖҒ家ж—ҸгӮ„иҰӘж—ҸгҒЁгғҲгғ©гғ–гғ«гҒ«гҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
гғҸгӮ«гӮ·гғ«гҒ§гҒҜгҒҠеў“гҒ®гғ—гғӯгҒ«зҙҚйӘЁе…ҲгӮ„гҒҠеў“гҒ®еј•гҒЈи¶ҠгҒ—гҒ®зӣёи«ҮгӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮжЁ№жңЁи‘¬гӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҒЁгҒҷгӮӢгҒ”йҒәйӘЁгҒ®зҙҚйӘЁгӮ’гҒӢгӮ“гҒҢгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒӘгӮүгғҸгӮ«гӮ·гғ«гҒ«гҒҠж°—и»ҪгҒ«гҒ”йҖЈзөЎгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
гӮӮгҒҸгҒҳ
жЁ№жңЁи‘¬гҒ®д»•зө„гҒҝгҒЁгҒҜпјҹиҮӘ然葬гҒЁгҒ®й–ўдҝӮгӮ„жӯҙеҸІгҒӢгӮүгӮҸгҒӢгӮӢж„Ҹе‘ігғ»е®ҡзҫ©
жЁ№жңЁи‘¬(гҒҳгӮ…гӮӮгҒҸгҒқгҒҶ)гҒҜгҖҒж•…дәәгҒ®гҒ”йҒәйӘЁгӮ’ж°ёд»ЈгҒ«з®ЎзҗҶгғ»дҫӣйӨҠгҒҷгӮӢж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҖҒжЁ№жңЁ(гӮ·гғігғңгғ«гғ„гғӘгғј)гғ»гҒҠиҠұгҒҢеў“жЁҷ(гҒҠеў“гҒ®гҒ—гӮӢгҒ—)гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
йғҪйҒ“еәңзңҢгҒӢгӮүиЁұеҸҜгӮ’еҫ—гҒҹеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз®ЎзҗҶгғ»йҒӢе–¶гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жЁ№жңЁи‘¬гҒ®еҹӢ葬方法гҒ®д»•зө„гҒҝ
гҒ”йҒәйӘЁгҒ®еҹӢ葬гҒ®ж–№жі•гҒҜгҖҒжЁ№жңЁгҒ®ж №жң¬гӮ„гҒҠиҠұгҒ®е‘ЁгӮҠгҒ«гҒқгҒ®гҒҫгҒҫеҹӢ葬гҒҷгӮӢгҖҒжңЁз¶ҝгӮ’гҒӨгҒӢгҒЈгҒҹеёғиўӢгҒ«еҢ…гӮ“гҒ§еҹӢ葬гҒҷгӮӢгҖҒеҫ®з”ҹзү©гҒӘгҒ©з”ҹзү©гҒ®дҪңз”ЁгҒ§еҲҶи§ЈгҒ•гӮҢгӮӢе®№еҷЁгҒ«гҒ”йҒәйӘЁгӮ’移гҒ—гҒҰеҹӢ葬гҒҷгӮӢж–№жі•гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жЁ№жңЁи‘¬гҒЁж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гғ»зҙҚйӘЁе ӮгҒ®гҒЎгҒҢгҒ„
жЁ№жңЁи‘¬гҒЁж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гҒ®гҒЎгҒҢгҒ„
жЁ№жңЁи‘¬гҒЁж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гҒҜеў“жЁҷгҒҢгҒЎгҒҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжЁ№жңЁи‘¬гҒ®еў“жЁҷгҒҜжЁ№жңЁгғ»гҒҠиҠұгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гҒҜгҖҒеў“зҹігҒҢеў“жЁҷгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзҙҚйӘЁе ҙжүҖгӮ„еҸӮжӢқгҒ®гӮ№гғҡгғјгӮ№гҒҜеұӢеӨ–гҒ«гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гҒҜгҖҒең°дёҠгҒ«еҸӮжӢқз”ЁгҒ®еғҸгғ»еЎ”гғ»зў‘(гғўгғӢгғҘгғЎгғігғҲ)гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒең°дёӢгҒ«гҒ”йҒәйӘЁгӮ’е®үзҪ®гҒҷгӮӢзҙҚйӘЁе®Ө(гӮ«гғӯгғјгғҲ)гҒҢгҒӮгӮӢгӮҝгӮӨгғ—гӮ„гҖҒең°дёҠгҒ«гҒ”йҒәйӘЁгӮ’е®үзҪ®гҒҷгӮӢжЈҡгҒҢгҒӮгӮӢгӮҝгӮӨгғ—гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жЁ№жңЁи‘¬гҒЁзҙҚйӘЁе ӮгҒ®гҒЎгҒҢгҒ„
жЁ№жңЁи‘¬гҒЁзҙҚйӘЁе ӮгҒҜгҒ”йҒәйӘЁгӮ’е®үзҪ®гҒҷгӮӢе ҙжүҖгҒҢгҒЎгҒҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзҙҚйӘЁе ӮгҒҜгҖҒеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ®ж•·ең°гҒ®гҒӘгҒӢгҒ®е»әзү©гҒ«зҙҚйӘЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
зҙҚйӘЁе ҙжүҖгӮ„еҸӮжӢқгҒ®гӮ№гғҡгғјгӮ№гҒҜеұӢеҶ…гҒ«гҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеӨ©еҖҷгҒ«е·ҰеҸігҒ•гӮҢгҒҡгҒ«еҸӮжӢқгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
зҙҚйӘЁе ӮгҒ«гҒҜгҖҒгӮігӮӨгғігғӯгғғгӮ«гғјгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«з®ұеһӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢзҙҚйӘЁеЈҮгҒ«йӘЁеЈәгӮ’е®үзҪ®гҒҷгӮӢгӮҝгӮӨгғ—гҖҒдёҠж®өгҒ«д»ҸеЈҮгғ»дҪҚзүҢгӮ’е®үзҪ®гҒ—гҒҰдёӢж®өгҒ«йӘЁеЈәгӮ’е®үзҪ®гҒҷгӮӢгӮҝгӮӨгғ—гҖҒеҸ—д»ҳгҒ«е°Ӯз”ЁгҒ®ICгӮ«гғјгғүгӮ’гҒӢгҒ–гҒҷгҒЁгҖҒеҸӮжӢқе®ӨгҒ«гҒ”йҒәйӘЁгҒҢгҒҜгҒ„гҒЈгҒҹе®№еҷЁгҒҢйҒӢгҒ°гӮҢгҒҰгҒҸгӮӢгӮҝгӮӨгғ—гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жЁ№жңЁи‘¬гҒҜжө·гӮ„еұұгҒ«гҒ”йҒәйӘЁгғ»гҒ”йҒәзҒ°гӮ’йӮ„гҒҷиҮӘ然葬гҒ®гҒІгҒЁгҒӨ
жЁ№жңЁи‘¬гҒҜгҒ”йҒәйӘЁ(гҒ”йҒәзҒ°)гӮ’жө·гӮ„еұұгҒӘгҒ©иҮӘ然гҒ«йӮ„гҒҷиҮӘ然葬гҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮиҮӘ然葬гҒ«гҒҜгҖҒжө·жҙӢ葬гғ»жЈ®жһ—葬(ж•ЈйӘЁ)гғ»гғҗгғ«гғјгғіи‘¬гғ»е®Үе®ҷ葬гғ»еңҹ葬гғ»йўЁи‘¬гғ»йіҘ葬гғ»ж°ҙ葬гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жө·жҙӢ葬гғ»жЈ®жһ—葬(ж•ЈйӘЁ)
жө·жҙӢ葬гҒҜжјҒжҘӯжЁ©гҒҢгҒӘгҒ„жө·гҒ®жІ–еҗҲгҒ§гҒ”йҒәйӘЁ(гҒ”йҒәзҒ°)гӮ’ж•ЈйӘЁгҒҷгӮӢ葬法гҖҒжЈ®жһ—葬гҒҜеұұеҘҘгҒ«гҒ”йҒәйӘЁ(йҒәзҒ°)гӮ’ж•ЈйӘЁгҒҷгӮӢ葬法гҒ§гҒҷгҖҒж•ЈйӘЁгҒ—гҒҹгҒӮгҒЁгҒҜзҢ®иҠұгӮ„зҢ®й…’гӮ’гҒ—гҒҰж•…дәәгӮ’дҫӣйӨҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ”йҒәйӘЁгӮ’гҒқгҒ®гҒҫгҒҫж•ЈйӘЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеҲ‘жі•190жқЎгҒ®йҒәйӘЁйҒәжЈ„зҪӘгҒ®иҰҸе®ҡгҒ§зҰҒжӯўгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒпҪўи‘¬йҖҒгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®зҘӯзҘҖгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒЁгҒ—гҒҰзҜҖеәҰгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгӮӢйҷҗгӮҠгҖҒйҒәйӘЁйҒәжЈ„зҪӘгҒ«гҒҜгҒӮгҒҹгӮүгҒӘгҒ„пҪЈгҒЁгҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒйҒәйӘЁгҒЁгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘзҠ¶ж…ӢгҒ§ж•ЈйӘЁгӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜзҰҒжӯўгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
еҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҒ®гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®ж•ЈйӘЁгҒ«й–ўгҒҷгӮӢгӮ¬гӮӨгғүгғ©гӮӨгғі(д»Өе’Ң3е№ҙ3жңҲ31ж—Ҙ)гҒҢжҺІијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒж•ЈйӘЁгҒҷгӮӢгҒ”йҒәйӘЁгҒ®е…·дҪ“зҡ„гҒӘеӨ§гҒҚгҒ•гҒҜе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
ж—Ҙжң¬жө·жҙӢж•ЈйӘЁеҚ”дјҡгҒ®гӮ¬гӮӨгғүгғ©гӮӨгғігҒ§гҒҜгҖҒгҒ”йҒәйӘЁгӮ’1mmпҪһ2mmзЁӢеәҰгҒ«зІүйӘЁгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒЁе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒ0.2mmд»ҘдёӢгҒ«з •гҒ„гҒҰгҒӢгӮүж•ЈйӘЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢжҘӯиҖ…гҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
еҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҒ®гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®ж•ЈйӘЁгҒ«й–ўгҒҷгӮӢгӮ¬гӮӨгғүгғ©гӮӨгғі
- гғ»йҷёдёҠ
- гҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒзү№е®ҡгҒ—гҒҹеҢәеҹҹ(жІіе·қеҸҠгҒіж№–жІјгӮ’йҷӨгҒҸгҖӮ)
- гғ»жө·жҙӢ
- жө·еІёгҒӢгӮүдёҖе®ҡгҒ®и·қйӣўд»ҘдёҠйӣўгӮҢгҒҹжө·еҹҹ(ең°зҗҶжқЎд»¶гҖҒеҲ©з”ЁзҠ¶жіҒзӯүгҒ®е®ҹжғ…гӮ’иёҸгҒҫгҒҲйҒ©еҲҮгҒӘи·қйӣўгӮ’иЁӯе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮ)
- гғ»з„јйӘЁгҒ®еӨ§гҒҚгҒ•
- гҒқгҒ®еҪўзҠ¶гӮ’иҰ–иӘҚгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶзІүзҠ¶гҒ«з •гҒҸгҒ“гҒЁгҖӮ
- еҸӮз…§е…ғпјҡеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҒ®гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®ж•ЈйӘЁгҒ«й–ўгҒҷгӮӢгӮ¬гӮӨгғүгғ©гӮӨгғі
ж—Ҙжң¬жө·жҙӢж•ЈйӘЁеҚ”дјҡгҒ®гӮ¬гӮӨгғүгғ©гӮӨгғі
- дәӢжҘӯиҖ…гҒҜгҖҒдәәгҒҢз«ӢгҒЎе…ҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢйҷёең°гҒӢгӮү1жө·йҮҢд»ҘдёҠйӣўгӮҢгҒҹжө·жҙӢдёҠгҒ®гҒҝгҒ§ж•ЈйӘЁгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒжІіе·қгҖҒж»қгҖҒе№ІжҪҹгҖҒжІіеҸЈд»ҳиҝ‘гҖҒгғҖгғ гҖҒж№–гӮ„жІјең°гҖҒжө·еІёгғ»жөңиҫәгғ»йҳІжіўе ӨгӮ„гҒқгҒ®иҝ‘иҫәгҒ§гҒ®ж•ЈйӘЁгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
- ж•ЈйӘЁгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«еҮәиҲӘгҒ—гҒҹиҲ№иҲ¶гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒ®гҒҝж•ЈйӘЁгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒгғ•гӮ§гғӘгғјгғ»йҒҠиҰ§иҲ№гғ»дәӨйҖҡиҲ№гҒӘгҒ©дёҖиҲ¬гҒ®иҲ№е®ўгҒҢгҒ„гӮӢиҲ№иҲ¶гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰж•ЈйӘЁгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
- жө·еІёгҒӢгӮүдёҖе®ҡгҒ®и·қйӣўд»ҘдёҠйӣўгӮҢгҒҹжө·еҹҹ(ең°зҗҶжқЎд»¶гҖҒеҲ©з”ЁзҠ¶жіҒзӯүгҒ®е®ҹжғ…гӮ’иёҸгҒҫгҒҲйҒ©еҲҮгҒӘи·қйӣўгӮ’иЁӯе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮ)
- жө·жҙӢдёҠгҒ§ж•ЈйӘЁгӮ’иЎҢгҒҶгҒ«йҡӣгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒжјҒе ҙгғ»йӨҠж®–е ҙгғ»иҲӘи·ҜгӮ’йҒҝгҒ‘гҖҒдёҖиҲ¬гҒ®иҲ№е®ўгҒӢгӮүиҰ–иӘҚгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«еҠӘгӮҒгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒ„гҒ‘гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
- еҸӮз…§е…ғпјҡж—Ҙжң¬жө·жҙӢж•ЈйӘЁеҚ”дјҡгҒ®гӮ¬гӮӨгғүгғ©гӮӨгғі
гғҗгғ«гғјгғіи‘¬
гҒ”йҒәйӘЁгӮ’еӨ§гҒҚгҒӘгғҗгғ«гғјгғі(йўЁиҲ№гғ»ж°—зҗғ)гҒ®гҒӘгҒӢгҒ«е…ҘгӮҢгҒҰгҖҒең°дёҠгҒӢгӮү10kmпҪһ50kmе…ҲгҒ®жҲҗеұӨеңҸгҒҫгҒ§дёҠжҳҮгҒ•гҒӣгҒҰз©әдёӯгҒ«ж•ЈйӘЁгҒҷгӮӢ葬法гҒ§гҒҷгҖӮ
гғҗгғ«гғјгғіи‘¬гӮ’гҒҷгӮӢе ҙжүҖгҒҜгҖҒжңҖдҪҺ10гҺЎеӣӣж–№(зёҰ10гғЎгғјгғҲгғ«Г—жЁӘ10гғЎгғјгғҲгғ«)гҒ®з©әгҒҚең°гҒ§гҖҒи§’еәҰ45еәҰгҒ®дёҠз©әд»ҳиҝ‘гҒ«й«ҳеұӨгғ“гғ«гӮ„йӣ»з·ҡгҒӘгҒ©гҖҒйҡңе®ізү©гҒҢз„ЎгҒ„е ҙжүҖгҒ§гҒҷгҖӮ
ж•…дәәгҒҢйҒҺгҒ”гҒ—гҒҰгҒҚгҒҹиҮӘе®…гҒ®еәӯгҖҒжҖқгҒ„еҮәгҒ®е ҙжүҖгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеёҢжңӣгҒ®е ҙжүҖгҒӢгӮүгғҗгғ«гғјгғігӮ’йЈӣгҒ°гҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
е®Үе®ҷ葬
е®Үе®ҷ葬гҒҜгҖҒгҒ”йҒәйӘЁ(гҒ”йҒәзҒ°)гӮ’葬е„Җе°Ӯй–ҖгҒ®иЎӣжҳҹгҒ®з„ЎдәәгғӯгӮұгғғгғҲгҖҒйҖҡдҝЎгҒ§еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢеӨ§еһӢгҒ®иЎӣжҳҹгӮ„жңҲйқўзқҖйҷёиҲ№гҒ«д№—гҒӣгҒҰгҖҒеӣҪйҡӣиҲӘз©әйҖЈзӣҹгҒ§е®ҡзҫ©гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе®Үе®ҷз©әй–“(ең°дёҠгҒӢгӮү100 km)гҒҫгҒ§жү“гҒЎдёҠгҒ’гҒҰж•ЈйӘЁгӮ’гҒҷгӮӢ葬法гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ”йҒәйӘЁгӮ’NASAгҒ®жңҲйқўжҺўжҹ»ж©ҹгҒ«д№—гҒӣгҒҰжңҲйқўгҒёйЈӣгҒ°гҒ—гҒҰжҺҘең°гҒ—гҒҹз®ҮжүҖгӮ’гҒҠеў“гҒ«гҒҷгӮӢжңҲйқўи‘¬гҒЁгҒ„гҒҶ葬法гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еңҹ葬
еңҹ葬гҒҜгҖҒгҒ”йҒәдҪ“гӮ’зҒ«и‘¬гҒ—гҒҹз„јйӘЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҒҰгҖҒгҒ”йҒәдҪ“гӮ’еҹӢ葬гҒҷгӮӢ葬法гҒ§гҒҷгҖӮгҒ”йҒәдҪ“гӮ’гҒқгҒ®гҒҫгҒҫеҹӢ葬гҒҷгӮӢж–№жі•гҒЁгҒ”йҒәдҪ“гӮ’жЈәгҒ«е…ҘгӮҢгҒҰеҹӢ葬гҒҷгӮӢж–№жі•гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еў“ең°еҹӢ葬法гҒ®з¬¬2жқЎгҒ§гҖҒжі•еҫӢдёҠгҒ®пҪўеҹӢ葬пҪЈгҒЁгҒҜжӯ»дҪ“гӮ’еңҹдёӯгҒ«и‘¬гӮӢгҒ“гҒЁгҒЁиЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒжі•еҫӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҹеў“ең°гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒеңҹдёӯгҒ«жӯ»дҪ“гӮ’еҹӢ葬гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜе•ҸйЎҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
еұұжўЁзңҢеҢ—жқңеёӮжҳҺйҮҺз”әгҒ®йўЁгҒ®дёҳйңҠең’гҖҒиҢЁеҹҺзңҢеёёз·ҸеёӮгҒ®жңұйӣҖгҒ®йғ·гҖҒеҢ—жө·йҒ“дҪҷеёӮйғЎгҒ®гӮҲгҒ„гҒЎйңҠең’гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еңҹ葬гҒҢгҒ§гҒҚгӮӢйңҠең’гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒеҗ„иҮӘжІ»дҪ“гҒ®жқЎдҫӢгӮ„еў“ең°з®ЎзҗҶиҖ…гҒҢе®ҡгӮҒгҒҹиҰҸеүҮгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеңҹ葬гҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„еҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
風葬
風葬гҒҜгҖҒгҒ”йҒәдҪ“гҒ«иЎЈгӮ’зқҖгҒӣгҒҰжңЁгҒ®дёҠгғ»жҙһзӘҹгғ»еҙ–гҒ«е®үзҪ®гҒ—гҒҰж—ҘгҒ®е…үгӮ„йӣЁгҒ«еҪ“гҒҰгҒҰзҷҪйӘЁеҢ–гӮ’еҫ…гҒӨ葬法гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ”йҒәдҪ“гҒҢзҷҪйӘЁеҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒӢгӮүгҒқгҒ®гҒҫгҒҫж”ҫзҪ®гҒҷгӮӢж–№жі•гҖҒзҷҪйӘЁеҢ–гҒ—гҒҹгҒ”йҒәйӘЁгӮ’ж°ҙгҒ§жҙ—гҒЈгҒҰ(жҙ—йӘЁ)гҖҒеҲҘгҒ®е ҙжүҖгҒ«е®үзҪ®гҒҷгӮӢж–№жі•гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ§йўЁи‘¬гҒҜзҰҒжӯўгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒе№іе®үжҷӮд»ЈгҒ«гҒҜдә¬йғҪгҒ§гҖҒжҲҰеүҚгҒҫгҒ§гҒҜжІ–зё„гҒ§гҒҠгҒ“гҒӘгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
йіҘ葬
йіҘ葬(еӨ©и‘¬)гҒҜгҖҒиӘӯзөҢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰйӯӮгҒҢжҠңгҒ‘гҒҹгҒ”йҒәдҪ“гҒ®иЎЈжңҚгӮ’еҸ–гӮҠеҺ»гҒЈгҒҰйҮҺеұұгӮ„еІ©гҒ®дёҠгҒӘгҒ©гҒ«зҪ®гҒ„гҒҰгҖҒйіҘ(дё»гҒ«гғҸгӮІгғҜгӮ·)гҒ«йЈҹгҒ№гҒ•гҒӣгҒҰеӨ©й«ҳгҒҸйҒӢгӮ“гҒ§гӮӮгӮүгҒҶ葬法гҒ§гҖҒгғҒгғҷгғғгғҲгҒ§гҒҠгҒ“гҒӘгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
дјјгҒҰгҒ„гӮӢ葬法гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгӮұгғӢгӮўеҚ—йғЁгҒӢгӮүгӮҝгғігӮ¶гғӢгӮўеҢ—йғЁгҒ®е…ҲдҪҸж°‘гғһгӮөгӮӨж—ҸгҒҢгҒҠгҒ“гҒӘгҒҶйҮҺз”ҹгҒ®зҚЈ(гғ©гӮӨгӮӘгғігғ»гғҸгӮӨгӮЁгғҠ)гҒ«гҒ”йҒәдҪ“гӮ’дёҺгҒҲгҒҰиҮӘ然гҒёйӮ„гҒҷзҚЈи‘¬(йҮҺ葬)гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
ж°ҙ葬
ж°ҙ葬гҒЁгҒҜгҖҒгҒ”йҒәдҪ“гӮ„гҒ”йҒәйӘЁгӮ’е·қгӮ„жө·гҒ«жөҒгҒҷ葬法гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒӢгҒҹгҒ®гҒ”йҒәдҪ“гғ»гҒ”йҒәйӘЁгӮ’е°ҸгҒ•гҒӘиҲҹгҒ«д№—гҒӣгҒҰжө·гҒ«жөҒгҒҷиҲҹ葬гҖҒдәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ”йҒәдҪ“гғ»гҒ”йҒәйӘЁгӮ’гҒқгҒ®гҒҫгҒҫжө·гҒ«жІҲгӮҒгӮӢжө·и‘¬гғ»е·қгҒ«жөҒгҒҷе·қ葬гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰзҰҒжӯўгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиҲ№иҲ¶гҒ®иҲӘиЎҢдёӯгҒ«д№—зө„е“Ўгғ»д№—е®ўгҒҢдәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒжқЎд»¶гӮ’жәҖгҒҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮҢгҒ°иҲ№й•·гҒ®жЁ©йҷҗгҒ§ж°ҙ葬гӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
жқЎд»¶
- жӯ»еҫҢ24жҷӮй–“гӮ’зөҢйҒҺгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢ(дјқжҹ“з—…д»ҘеӨ–)
- иЎӣз”ҹдёҠгҖҒйҒәдҪ“гӮ’иҲ№еҶ…гҒ«дҝқеӯҳгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„зҠ¶жіҒгҒ§гҒӮгӮӢ
- еҢ»её«гҒҢгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҜжӯ»дәЎиЁәж–ӯжӣёгӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢ
- жң¬дәәгҒ®еҶҷзңҹж’®еҪұгҖҒйҒәе“ҒгҖҒйҒәй«ӘгҒ®дҝқз®ЎгӮ’гҒҷгӮӢ
- йҒәдҪ“гҒҢжө®гҒҚдёҠгҒҢгӮүгҒӘгҒ„еҮҰзҪ®гӮ’гҒҷгӮӢ
- зӣёеҝңгҒ®е„ҖзӨјгӮ’е°ҪгҒҸгҒҷ
- ж¶ҲжҜ’гӮ„йҒәдҪ“гҒ®еҮҰзҪ®гӮ’йҒ©еҲҮгҒ«гҒҷгӮӢзӯү
иҲҹ葬гҒҜгӮ№гӮҰгӮ§гғјгғҮгғігӮ„гғҺгғ«гӮҰгӮ§гғјгҒ§гҖҒжө·и‘¬гҒҜгғқгғӘгғҚгӮ·гӮўгӮ„гӮўгғЎгғӘгӮ«гғ»гӮӨгғігғҮгӮЈгӮўгғігҒ§гҒҠгҒ“гҒӘгӮҸгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
е·қ葬гҒҜгӮӨгғігғүгҒ®гӮ¬гғігӮёгӮ№е·қгҒ§зҸҫеңЁгӮӮгҒҠгҒ“гҒӘгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзҒ«и‘¬е ҙгҒ§зҒ«и‘¬гҒ—гҒҹз„јйӘЁгӮ’гҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒЁдёҖз·’гҒ«гӮ¬гғігӮёгӮ№е·қгҒ«йҒӢгӮ“гҒ§жөҒгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жЁ№жңЁи‘¬гҒ®жӯҙеҸІ
1991е№ҙ10жңҲгҒ«зҘһеҘҲе·қзңҢзӣёжЁЎзҒҳжІ–гҒ§ж•ЈйӘЁ
葬йҖҒгҒ®иҮӘз”ұгӮ’гҒҷгҒҷгӮҒгӮӢдјҡгҒҢ1991е№ҙ10жңҲгҒ«зҘһеҘҲе·қзңҢзӣёжЁЎзҒҳжІ–гҒ§ж•ЈйӘЁгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒжі•еӢҷзңҒгҒЁеҺҡз”ҹзңҒ(зҸҫеҺҡеҠҙзңҒ)гҒ®йқһе…¬ејҸгҒ®иҰӢи§ЈгҒ§гҖҒйҒ•жі•гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁж–ӯиЁҖгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүдё–й–“гҒ®жіЁзӣ®гӮ’йӣҶгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
- жі•еӢҷзңҒгҒ®йқһе…¬ејҸгҒ®иҰӢи§Ј
- пҪўи‘¬йҖҒгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®зҘӯзҘҖгҒЁгҒ—гҒҰзҜҖеәҰгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгӮӢйҷҗгӮҠйҒәйӘЁйҒәжЈ„зҪӘгҒ«и©ІеҪ“гҒ—гҒӘгҒ„пҪЈ
- еҺҡз”ҹзңҒ(зҸҫеҺҡеҠҙзңҒ)гҒ®йқһе…¬ејҸгҒ®иҰӢи§Ј
- пҪўеў“ең°еҹӢ葬法гҒҜгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁеңҹ葬гӮ’е•ҸйЎҢгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгҖҒйҒәзҒ°гӮ’жө·гӮ„еұұгҒ«гҒҫгҒҸгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹ葬法гҒҜжғіе®ҡгҒ—гҒҰгҒҠгӮүгҒҡгҖҒеҜҫиұЎеӨ–гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ гҒӢгӮүгҒ“гҒ®жі•еҫӢгҒҜиҮӘ然葬гӮ’зҰҒгҒҡгӮӢиҰҸе®ҡгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„пҪЈ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжө·жҙӢж•ЈйӘЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгғ»гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ«гҒӢгҒӢгӮҸгӮӢжі•зҡ„гҒӘж №жӢ гҒҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒйҒ•жі•гҒӘгҒ®гҒӢгҖҒйҒ©жі•гҒӘгҒ®гҒӢиӯ°и«–гҒҢзө¶гҒҲгҒҡгҖҒжө·жҙӢж•ЈйӘЁгҒЁгҒҜгҒЎгҒҢгҒҶиҮӘ然葬гӮ’жұӮгӮҒгӮӢгҒӢгҒҹгҒҢеў—гҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
1999е№ҙгҒ«еІ©жүӢзңҢгҒ®зҘҘйӣІеҜә(зҸҫпјҡзҹҘеӢқйҷў)гҒ§жЁ№жңЁи‘¬гҒҢиӘ•з”ҹ
1999е№ҙгҒ«еІ©жүӢзңҢгҒ®зҘҘйӣІеҜә(зҸҫпјҡзҹҘеӢқйҷў)гҒ«гҒ”йҒәйӘЁгҒ®иҝ‘гҒҸгҒ«дҪҺжңЁйЎһгҒ®жЁ№жңЁгӮ’жӨҚгҒҲгҒҰйҮҢеұұгҒ®з·‘еҢ–еҶҚз”ҹгӮ’е…јгҒӯгӮӢжЁ№жңЁи‘¬гҒҢиӘ•з”ҹгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
2004е№ҙгҒ«еҢ—жө·йҒ“й•·жІјз”әгҒ§жЁ№жңЁи‘¬еў“ең°е•ҸйЎҢгҒҢзҷәз”ҹ
2004е№ҙгҒ«еҢ—жө·йҒ“й•·жІјз”әгҒ§гғӣгғӯгғҠгӮӨжЁ№жңЁи‘¬жЈ®жһ—е…¬ең’гҒ§еў“ең°д»ҘеӨ–гҒ®е ҙжүҖгҒ§ж•ЈйӘЁгҒҷгӮӢжЁ№жңЁи‘¬гҒҢе•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮең°еҹҹгҒ®дҪҸж°‘гҒ®еҸҚеҜҫйҒӢеӢ•гӮ’гҒ—гҒҹзөҗжһңгҖҒй•·жІјз”әиӯ°дјҡгҒҢеў“ең°жҢҮе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹе ҙжүҖгҒ§гҒ—гҒӢж•ЈйӘЁгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶжқЎдҫӢгӮ’еҲ¶е®ҡгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
2006е№ҙгҒ«зҘһеҘҲе·қзңҢжЁӘжөңеёӮгҒ®йңҠең’гҒ§еҲқгҒ®е…¬е–¶гҒ®жЁ№жңЁи‘¬гҒҢиӘ•з”ҹ
2006е№ҙгҒ«зҘһеҘҲе·қзңҢжЁӘжөңеёӮгҒ®пҪўжЁӘжөңеёӮе–¶гғЎгғўгғӘгӮўгғ«гӮ°гғӘгғјгғіпҪЈгҒ§еҲқгӮҒгҒҰгҒ®е…¬е–¶гҒ®жЁ№жңЁи‘¬гҒҢиӘ•з”ҹгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
2006е№ҙд»ҘйҷҚгҖҒдәәеҸЈгҒҢеӨҡгҒҸгҒҰеў“ең°дёҚи¶ігҒҢе•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢйғҪеёӮйғЁгӮ’дёӯеҝғгҒ«гҖҒжЁ№жңЁи‘¬гҒҢжҷ®еҸҠгҒ—е§ӢгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ2012е№ҙгҒ«гҒҜе°Ҹе№ійңҠең’гҒ«йғҪз«ӢйңҠең’еҲқгҒ®жЁ№жһ—еў“ең°гҒҢиӘ•з”ҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
2022е№ҙзҸҫеңЁ ж•ҙеӮҷгҒҢйҖІгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢжЁ№жңЁи‘¬
е…¬е…ұгғ»ж°‘й–“гӮ’е•ҸгӮҸгҒҡгҒ«жЁ№жңЁи‘¬гҒ®еҢәз”»гҒҢеў—гҒҲз¶ҡгҒ‘гҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒйңҠең’гҒ®дёҖйғЁгҒ®еҢәз”»гӮ’ж•ҙеӮҷгҒ—гҒҰгҒӨгҒҸгӮүгӮҢгҒҹжЁ№жңЁи‘¬еў“ең°гҒҢеӨҡгҒ„гҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒеҹӢ葬гҒ—гҒҹгҒ”йҒәйӘЁгҒҢиҮӘ然гҒ«йӮ„гӮӢжЁ№жңЁи‘¬еў“ең°гӮ’жұӮгӮҒгӮӢеЈ°гҒҢеӨҡгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иҮӘ然葬гғ»жЁ№жңЁи‘¬гӮ’йҒёгӮ“гҒ иҠёиғҪдәәдёҖиҰ§
жЁ№жңЁи‘¬гӮ’йҒёгӮ“гҒ иҠёиғҪдәә
- з”°дёӯи§’ж „з ”з©¶гҒ§зҹҘгӮүгӮҢгӮӢз«ӢиҠұйҡҶгҒ•гӮ“(2021е№ҙйҖқеҺ»)
- еҘіе„ӘгҒ®еёӮеҺҹжӮҰеӯҗгҒ•гӮ“(2019е№ҙйҖқеҺ»)
- е°ҸиӘ¬е®¶гҒ®еі¶гӮүгӮӮгҒ•гӮ“(2004е№ҙйҖқеҺ»)
иҮӘ然葬гғ»жЁ№жңЁи‘¬гӮ’йҒёгӮ“гҒ иҠёиғҪдәәдёҖиҰ§
иҮӘ然葬гӮ’йҒёгӮ“гҒ иҠёиғҪдәәгғ»жңүеҗҚдәә
- дҝіе„ӘгҒ®еӢқж–°еӨӘйғҺгҒ•гӮ“(1997е№ҙйҖқеҺ»)
- жј«жүҚеё«гҒ®жЁӘеұұгӮ„гҒҷгҒ—гҒ•гӮ“(1996е№ҙйҖқеҺ»)
- дҝіе„Әгғ»жӯҢжүӢгҒ®зҹіеҺҹиЈ•ж¬ЎйғҺгҒ•гӮ“(1987е№ҙйҖқеҺ»)
- дҪң家гғ»е…ғжқұдә¬йғҪзҹҘдәӢгҒ®зҹіеҺҹж…ҺеӨӘйғҺгҒ•гӮ“(2022е№ҙйҖқеҺ»)
жЁ№жңЁи‘¬гҒ«зҙҚйӘЁгҒҷгӮӢжүӢз¶ҡгҒҚгҒ®жөҒгӮҢгӮ„ж–№жі•гғ»жңҚиЈ…гӮ’зҙ№д»Ӣ
жЁ№жңЁи‘¬гҒ«зҙҚйӘЁгҒҷгӮӢжҷӮжңҹгҒҜеӣӣеҚҒд№қж—ҘгҒҢеӨҡгҒ„
д»Ҹж•ҷгҒ§гҒҜе‘Ҫж—ҘгҒӢгӮү49ж—ҘеҫҢгҒ«ж•…дәәгҒ®йӯӮгҒ®иЎҢгҒҚе…ҲгҒҢжұәгҒҫгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒжЁ№жңЁи‘¬гҒ§гҒҜе‘Ҫж—ҘгҒӢгӮү49ж—Ҙзӣ®гҒ«еӣӣеҚҒд№қж—Ҙжі•иҰҒгҒҠгҒ“гҒӘгҒЈгҒҰж•…дәәгҒ®гҒ”йҒәйӘЁгӮ’зҙҚйӘЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
жЁ№жңЁи‘¬гҒ«зҙҚйӘЁгҒҷгӮӢзҙҚйӘЁејҸгҒ®жөҒгӮҢ
гҒҠеқҠгҒ•гӮ“гӮӮгҒ—гҒҸгҒҜгҖҒеў“ең°гҒ®з®ЎзҗҶдәӢеӢҷе“ЎгҒЁиӘҝж•ҙгҒ—гҒҹж—ҘгҒ«гҖҒжҢҮе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹе ҙжүҖгҒёдјәгҒЈгҒҰеҹӢ葬иЁұеҸҜиЁјгғ»еҘ‘зҙ„жӣёгҒ®жҸҗеҮәгҖҒиІ»з”Ёгғ»гҒҠеёғж–ҪгҒ®ж”Ҝжү•гҒ„гӮ’гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
зҙҚйӘЁгҒҷгӮӢе ҙжүҖгҒ«з§»еӢ•гҒ—гҒҹгҒӮгҒЁгҒҜгҖҒгҒ”йҒәйӘЁгҒ®зҙҚйӘЁгҖҒгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«гӮҲгӮӢиӘӯзөҢгҖҒгҒҠз·ҡйҰҷгӮ’гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
ж°‘е–¶йңҠең’гғ»е…¬е–¶йңҠең’гҒ®е ҙеҗҲгҖҒгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«гӮҲгӮӢиӘӯзөҢгӮ’еёҢжңӣгҒҷгӮӢгҒӘгӮүдәӢеүҚгҒ«иӘӯзөҢгӮ’гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮӢгҒ®гҒӢгҖҒгҒ„гҒҸгӮүгҒӢгҒӢгӮӢгҒӢгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
жЁ№жңЁи‘¬гҒ«зҙҚйӘЁгҒҷгӮӢзҙҚйӘЁејҸгҒ®жңҚиЈ…
йңҠең’еһӢжЁ№жңЁи‘¬гҒ®зҙҚйӘЁејҸгҒ®жңҚиЈ…гҒҜе–ӘжңҚгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ葬е„ҖгҒ§зқҖз”ЁгҒ—гҒҹе–ӘжңҚгҒ§еҸӮеҲ—гҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒдәӢеүҚгҒ«жұҡгӮҢгҒҢгҒӘгҒ„гҒӢзўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
йҮҢеұұеһӢжЁ№жңЁи‘¬гҒ®зҙҚйӘЁејҸгҒ®жңҚиЈ…гҒҜгҖҒеұұгҒ®гҒӘгҒӢгӮ’жӯ©гҒ‘гӮӢеӢ•гҒҚгӮ„гҒҷгҒ„жңҚиЈ…гҒ§гҒ„гҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгӮ·гғЈгғ„гҒҜиҘҹд»ҳгҒҚгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§жҹ„гҒҢгҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„йҒӢеӢ•зқҖгҖҒгғ‘гғігғ„гҒҜиүІгҒ®жҡ—гҒ„йҒӢеӢ•зқҖгҖҒйқҙгҒҜй»’гҒӘгҒ©гҒ®жҡ—гҒ„иүІгҒ®йҒӢеӢ•йқҙгҒҢжңӣгҒҫгҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
йӣЁгҒҢйҷҚгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒӘгӮүгҖҒгӮігғјгғҲгӮ’зқҖз”ЁгҒ—гҒҹгҒҫгҒҫзҙҚйӘЁејҸгҒ«еҸӮеҲ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
жЁ№жңЁи‘¬гҒ«гҒ—гҒҹеҫҢгҒ®жі•иҰҒгӮ„гҒҠеў“еҸӮгӮҠгғ»гҒҠдҫӣгҒҲгҒ®гғһгғҠгғј
жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒ®жңҚиЈ…
| еӣӣеҚҒд№қж—Ҙ | дёҖе‘ЁеҝҢ | дёүеӣһеҝҢд»ҘйҷҚ | гҒҠеў“еҸӮгӮҠ | |
|---|---|---|---|---|
| йңҠең’еһӢ | жӯЈе–ӘжңҚ жә–е–ӘжңҚ |
жӯЈе–ӘжңҚ жә–е–ӘжңҚ |
з•ҘејҸжӯЈиЈ… | жҢҮе®ҡгҒӘгҒ— |
| йҮҢеұұеһӢ | йҒӢеӢ•зқҖ | йҒӢеӢ•зқҖ | йҒӢеӢ•зқҖ | йҒӢеӢ•зқҖ |
йңҠең’еһӢжЁ№жңЁи‘¬гҒ®е ҙеҗҲгҖҒ еӣӣеҚҒд№қж—ҘгҒЁдёҖе‘ЁеҝҢгҒ®жңҚиЈ…гҒҜгҖҒйҒәж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸгҒӘгӮүжӯЈе–ӘжңҚгғ»жә–е–ӘжңҚгҖҒеҸӮеҲ—иҖ…гҒӘгӮүй»’гғ»зҙәгғ»гӮ°гғ¬гғјгҒ®гӮ№гғјгғ„(з”·жҖ§)гҖҒй»’гҒ„гғ–гғ©гӮҰгӮ№гӮ„гӮ№гӮ«гғјгғҲгҒ«й»’гӮӮгҒ—гҒҸгҒҜгғҷгғјгӮёгғҘгҒ®гӮ№гғҲгғғгӮӯгғігӮ°(еҘіжҖ§)гҒ®з•ҘејҸжӯЈиЈ…гҒ§еҸӮеҲ—гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
дёүеӣһеҝҢд»ҘйҷҚгҒ®жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒ®жңҚиЈ…гҒҜгҖҒйҒәж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸгҒҠгӮҲгҒіеҸӮеҲ—иҖ…гҒЁгӮӮгҒ«з•ҘејҸжӯЈиЈ…гҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ§гҒҷгҖӮ
жңҖдҪҺйҷҗгҒ®иә«гҒ гҒ—гҒӘгҒҝгӮ„жё…жҪ”ж„ҹгҒҜеӨ§дәӢгҒ«гҒ—гҒҹгҒ»гҒҶгҒҢгҒ„гҒ„гҒ®гҒ§гҖҒжҙҫжүӢгҒӘжңҚиЈ…гӮ„гғҺгғјгӮ№гғӘгғјгғ–гғ»гӮҝгғігӮҜгғҲгғғгғ—гғ»гғҸгғјгғ•гғ‘гғігғ„гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹиӮҢгҒ®йңІеҮәгҒҢеӨҡгҒ„жңҚиЈ…гҒҜйҒҝгҒ‘гҒҹгҒ»гҒҶгҒҢгҒ„гҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
еҗҲзҘҖеһӢжЁ№жңЁи‘¬гҒҜгҖҒ他家гҒ®еҸӮеҲ—иҖ…гҒҢгҒҸгӮӢгҒ®гҒ§еӨұзӨјгҒ®гҒӘгҒ„жңҚиЈ…гҒ§еҸӮеҲ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ®гҒһгҒҫгҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
йҮҢеұұеһӢжЁ№жңЁи‘¬гҒ®жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒ®жңҚиЈ…гҒҜгҖҒеұұгҒ®гҒӘгҒӢгӮ’жӯ©гҒ‘гӮӢеӢ•гҒҚгӮ„гҒҷгҒ„жңҚиЈ…гҒ§гҒ„гҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгӮ·гғЈгғ„гҒҜиҘҹд»ҳгҒҚгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§жҹ„гҒҢгҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„йҒӢеӢ•зқҖгҖҒгғ‘гғігғ„гҒҜиүІгҒ®жҡ—гҒ„йҒӢеӢ•зқҖгҖҒйқҙгҒҜй»’гҒӘгҒ©гҒ®жҡ—гҒ„иүІгҒ®зҷ»еұұйқҙгғ»гӮ№гғӢгғјгӮ«гғјгҒҢжңӣгҒҫгҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
йҮҢеұұеһӢжЁ№жңЁи‘¬гҒҜеұұеҘҘгҒ«гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒж°ҙзӯ’гҒӘгҒ©ж°ҙеҲҶиЈңзөҰгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮӮгҒ®гӮ’жҢҒеҸӮгҒҷгӮӢгҖҒйӣЁгҒҢйҷҚгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢж—ҘгӮ„йўЁгҒҢеј·гҒ„ж—ҘгҒҜйҒҝгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҠдҫӣгҒҲгҒ®гғһгғҠгғј
еұұзҒ«дәӢйҳІжӯўгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒҠз·ҡйҰҷгӮ„гӮҚгҒҶгҒқгҒҸгӮ’жҢҒгҒЎиҫјгӮҒгҒӘгҒ„гҖҒгҒҠж°ҙгӮ’е…ҘгӮҢгҒҰиҠұ瓶гӮ’иЁӯзҪ®гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶиҰҸеүҮгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
йҮҢеұұеһӢжЁ№жңЁи‘¬гҒҜгҖҒгҒ©гҒ®жЁ№жңЁгҒ®гӮӮгҒЁгҒ«гҒ”йҒәйӘЁгҒҢеҹӢ葬гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢдёҖиҰӢгҒҷгӮӢгҒЁгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒзӣ®еҚ°гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҰгҒҠгҒҸгҒЁгҒ„гҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ