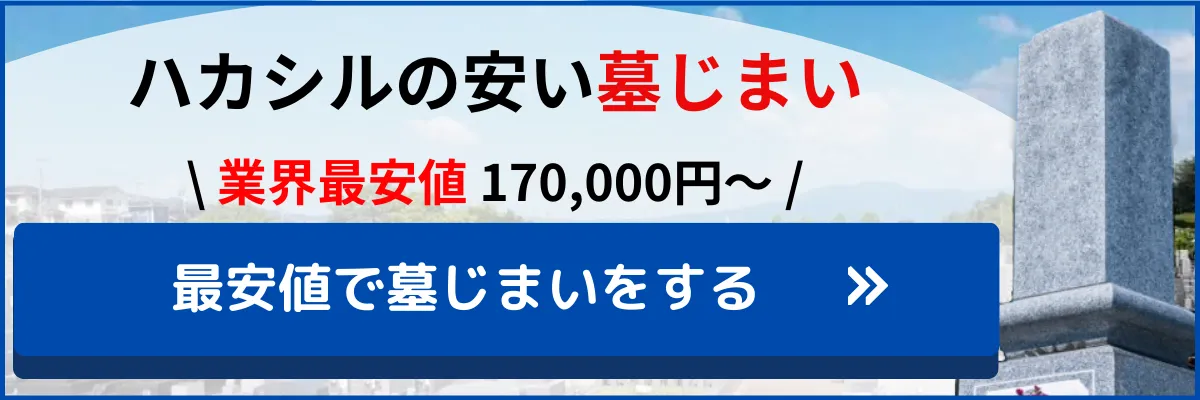ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеҫҢгҒ®дҫӣйӨҠгғ»жі•иҰҒгҒЁжҠ‘гҒҲгӮӢгҒ№гҒҚгҒҠеёғж–ҪгҒ®зӣёе ҙгӮ„гҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒ®гғһгғҠгғј
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§зҙҚйӘЁгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒ®иӘӯзөҢгҖҒжҳҘгғ»з§ӢгҒ®гҒҠеҪјеІёгҒ«гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶдҫӣйӨҠгҖҒе№ҙеҝҢжі•иҰҒгҒ«гӮҲгӮӢдҫӣйӨҠгҖҒзҘҘжңҲе‘Ҫж—Ҙ(гҒ—гӮҮгҒҶгҒӨгҒҚгӮҒгҒ„гҒ«гҒЎ)гҒ®дҫӣйӨҠгҖҒжңҲе‘Ҫж—ҘгҒ®дҫӣйӨҠгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒдҫӣйӨҠгғ»жі•иҰҒгҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гӮ„еӣһж•°гҒҜеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒЎгҒҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ§гӮӮгҒҠеёғж–ҪгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒҠеёғж–ҪгҒ®зӣёе ҙгҒҜ3дёҮеҶҶпҪһ5дёҮеҶҶзЁӢеәҰгҒ§гҒҷгҖӮ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®дҫӣйӨҠгғ»жі•иҰҒгҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гӮ„еӣһж•°гҖҒгҒҠеёғж–ҪгҒ®зӣёе ҙгӮ„гҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒ®гғһгғҠгғјгӮ’зҹҘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҖҒгҒ”йҒәж—ҸгӮ„иҰӘж—ҸгҖҒеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒЁгғҲгғ©гғ–гғ«гҒ«гҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҫҢжӮ”гҒҷгӮӢеүҚгҒ«гҖҒгӮҲгҒҸгҒҠгҒ“гҒӘгӮҸгӮҢгӮӢдҫӣйӨҠгғ»жі•иҰҒгҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гӮ„еӣһж•°гҖҒгҒҠеёғж–ҪгӮ„гҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒ®гғһгғҠгғјгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гӮӮгҒҸгҒҳ
- 1)ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®дҫӣйӨҠгғ»жі•иҰҒгҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒЁеӣһж•°
- 2)ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ—гҒҹеҫҢгҒ«е®¶ж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸеҒҙгҒ§жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶеҝ…иҰҒжҖ§
- 3)ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ—гҒҹеҫҢгҒ®жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒ®жөҒгӮҢгӮ„гҒҠеёғж–ҪгҒ®зӣёе ҙгҒЁжёЎгҒ—ж–№
- 4)ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ—гҒҹеҫҢгҒ®гҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒ®ж–№жі•гғ»гҒҠдҫӣгҒҲгғ»гғһгғҠгғј
- 5)ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ—гҒҹеҫҢгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢиІ»з”Ё
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®дҫӣйӨҠгғ»жі•иҰҒгҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒЁеӣһж•°
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒЁгҒҜгҖҒж°ёд»ЈгҒ«гӮҸгҒҹгҒЈгҒҰзҙҚйӘЁгҒ—гҒҹгҒӮгҒЁгҒ®дҫӣйӨҠгғ»з®ЎзҗҶгӮ’еҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ«д»»гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢдҫӣйӨҠж–№жі•гҒ§гҒҷгҖӮгҒҠеў“гҒ®жҺғйҷӨгӮ„дҝ®з№•гҖҒзҜҖзӣ®гҒ”гҒЁгҒ®дҫӣйӨҠгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒҜгҖҒгҒҠеў“гӮ’еҸ—гҒ‘з¶ҷгҒҗгҒ“гҒЁгӮ’еүҚжҸҗгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгӮ„еӯ«гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒҠеў“гҒ®еҫҢз¶ҷиҖ…гҒҢгҒ„гҒӘгҒҸгҒҰгӮӮе®үеҝғгҒ—гҒҰеҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®дҫӣйӨҠгғ»жі•иҰҒгҒҜгҖҒеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒҢе®ҡжңҹзҡ„гҒ«гҒҠгҒ“гҒӘгҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдҫӣйӨҠгғ»жі•иҰҒгҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гӮ„еӣһж•°гҒҜеҜәйҷўгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дҫӣйӨҠгғ»жі•иҰҒгҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°
- зҙҚйӘЁгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒ®иӘӯзөҢ
- жҳҘгғ»з§ӢгҒ®гҒҠеҪјеІёгҒ«гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶдҫӣйӨҠ
- е№ҙеҝҢжі•иҰҒгҒ«гӮҲгӮӢдҫӣйӨҠ
- зҘҘжңҲе‘Ҫж—Ҙ(гҒ—гӮҮгҒҶгҒӨгҒҚгӮҒгҒ„гҒ«гҒЎ)гҒ®дҫӣйӨҠ
- жңҲе‘Ҫж—ҘгҒ®дҫӣйӨҠ
- жҜҺжңҲ1еӣһгғ»жҜҺж—ҘгҒ®дҫӣйӨҠ
зҙҚйӘЁгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒ®иӘӯзөҢ
гҒ”йҒәйӘЁгӮ’зҙҚйӘЁгҒ—гҒҹгҒӮгҒЁгҒ«гҖҒж•…дәәгҒ®еҶҘзҰҸгӮ’зҘҲгӮӢж°—жҢҒгҒЎгӮ’иҫјгӮҒгҒҰгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«иӘӯзөҢгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮиӘӯзөҢгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӮгҒ„гҒ гҖҒеҸӮеҲ—иҖ…гҒҜз„јйҰҷгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
йҖҡеёёгҖҒгҒҠеў“гҒ«гҒ”йҒәйӘЁгӮ’зҙҚйӘЁгӮ’гҒҷгӮӢгҒҫгҒҲгҒ«еӣӣеҚҒд№қж—Ҙжі•иҰҒ(ж•…дәәгҒ®йӯӮгҒ®иЎҢгҒҚе…ҲгҒҢжұәгҒҫгӮӢе‘Ҫж—ҘгҒӢгӮү49ж—ҘеҫҢгҒ«гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶжі•иҰҒ)гӮ’гҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ«гҒҜеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒйҒәж—ҸгҒҢеёҢжңӣгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒеҲҘйҖ”жүӢй…ҚгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еӣӣеҚҒд№қж—Ҙжі•иҰҒ(еҝҢж—Ҙжі•иҰҒ)гӮ’гҒҷгӮӢзҗҶз”ұ
еӣӣеҚҒд№қж—Ҙжі•иҰҒгҒҜгҖҒж•…дәәгҒҢдәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹж—ҘгӮ’еҝҢж—ҘгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҝҢж—ҘгҒӢгӮү7ж—ҘгҒ”гҒЁгҒ«гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶеҝҢж—Ҙжі•иҰҒгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҖҒж•…дәәгҒҢд»ҸгҒЁгҒ—гҒҰжҘөжҘҪжө„еңҹгҒёиҝҺгҒҲе…ҘгӮҢгӮүгӮҢгӮӢ(жҲҗд»ҸгҒҷгӮӢ)гӮҲгҒҶгҒ«гҒҠзҘҲгӮҠгҒҷгӮӢжі•иҰҒгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
еҝҢж—Ҙжі•иҰҒгҒҜгҖҒеҲқдёғж—Ҙ(гҒ—гӮҮгҒӘгҒ®гҒӢ)гҖҒдәҢдёғж—Ҙ(гҒөгҒҹгҒӘгҒ®гҒӢ)гҖҒдёүдёғж—Ҙ(гҒҝгҒӘгҒ®гҒӢ)гҖҒеӣӣдёғж—Ҙ(гӮҲгҒӘгҒ®гҒӢ)гҖҒдә”дёғж—Ҙ(гҒ„гҒӨгҒӘгҒ®гҒӢ)гҖҒе…ӯдёғж—Ҙ(гӮҖгҒӘгҒ®гҒӢ)гҖҒдёғдёғж—Ҙ(гҒӘгҒӘгҒӘгҒ®гҒӢ)гҒЁз¶ҡгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
зҸҫеңЁгҒҜгҖҒеҲқдёғж—ҘгҒ®жі•иҰҒгӮ’е‘ҠеҲҘејҸгҒ®гҒӮгҒЁгҒ«гҖҒеӣӣеҚҒд№қж—ҘгҒ®жі•иҰҒгӮ’зҙҚйӘЁгӮ’гҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
жҳҘгғ»з§ӢгҒ®гҒҠеҪјеІёгҒ«гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶдҫӣйӨҠ
жҳҘгҒ®гҒҠеҪјеІёгҒҜ3жңҲгҒ®жҳҘеҲҶгҒ®ж—ҘгӮ’зңҹгӮ“дёӯгҒ®ж—ҘгҒЁгҒ—гҒҰеүҚеҫҢ3ж—Ҙй–“гҖҒз§ӢгҒ®гҒҠеҪјеІёгҒҜ9жңҲгҒ®з§ӢеҲҶгҒ®ж—ҘгӮ’зңҹгӮ“дёӯгҒ®ж—ҘгҒЁгҒ—гҒҰеүҚеҫҢ3ж—Ҙй–“гҒ®еҗҲиЁҲ7ж—Ҙй–“гҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҒ„гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жҳҘгғ»з§ӢгҒ®гҒҠеҪјеІёгҒ®жҷӮжңҹгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒиҝ‘гҒ„ж—ҘгӮ’йҒёгӮ“гҒ§гҒҠгҒ“гҒӘгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
е№ҙеҝҢжі•иҰҒгҒ«гӮҲгӮӢдҫӣйӨҠ
е№ҙеҝҢжі•иҰҒгҒҜгҖҒдёҖе‘ЁеҝҢгӮ„дёүе‘ЁеҝҢгҒӘгҒ©д»Ҹж•ҷгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжұәгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢзҜҖзӣ®гҒ®е№ҙгҒ®ж•…дәәгҒ®е‘Ҫж—ҘгҒ«гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶдҫӣйӨҠгҒ§гҒҷгҖӮ
е№ҙеҝҢжі•иҰҒгҒ®дҫӣйӨҠгҒ®ж–№жі•гҒҜеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒЎгҒҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ®иЎҢдәӢгҒ«гҒӮгӮҸгҒӣгҒҰе№ҙеҝҢжі•иҰҒгҒ®е№ҙеәҰгҒ«гҒӮгҒҹгӮӢж•…дәәгҒ®жҲ’еҗҚгӮ’гҒҫгҒЁгӮҒгҒҰиӘӯгҒҝдёҠгҒ’гӮӢж–№жі•гҒЁгҖҒзҙҚйӘЁгҒ—гҒҹеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ®гҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«еҖӢеҲҘгҒ«е№ҙеҝҢжі•иҰҒгӮ’гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж–№жі•гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ®иЎҢдәӢгҒ«гҒӮгӮҸгҒӣгҒҰе№ҙеҝҢжі•иҰҒгҒ«гӮҲгӮӢдҫӣйӨҠгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶе ҙеҗҲгҒҜгҖҒгҒ”йҒәж—ҸгҒ®еҸӮеҲ—гҖҒгҒҠеёғж–ҪгҒ®ж”Ҝжү•гҒ„гҒҜеҝ…иҰҒгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒе№ҙеҝҢжі•иҰҒгҒ®ж—ҘгҒҢгҒ”йҒәж—ҸеҒҙгҒ§йҒёгҒ№гҒӘгҒ„гҖҒгҒ»гҒӢгҒ®ж•…дәәгҒЁеҗҲеҗҢгҒ®жі•иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«жіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
е№ҙеҝҢжі•иҰҒгӮ’гҒҷгӮӢзҗҶз”ұ
д»Ҹж•ҷгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒд»ҸгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹж•…дәәгҒҜдёҖе‘ЁеҝҢгҖҒдёүеӣһеҝҢгҖҒдёғеӣһеҝҢгҖҒеҚҒдёүеӣһеҝҢгҖҒеҚҒдёғеӣһеҝҢгҖҒдәҢеҚҒдёүеӣһеҝҢгҖҒдәҢеҚҒдёғеӣһеҝҢгҖҒдёүеҚҒдёүеӣһеҝҢгҒЁй•·гҒ„дҝ®иЎҢгӮ’гҒ—гҒҰгҖҒиҸ©и–©(гҒјгҒ•гҒӨ)гҒ®йҒ“гҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҖҒе®ҲгӮҠзҘһ(гҒ”е…ҲзҘ–гҒ•гҒҫ)гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«гҖҒдә”еҚҒеӣһеҝҢгҖҒзҷҫеӣһеҝҢгҒЁз¶ҡгҒҚгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдёүеҚҒдёүеӣһеҝҢгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒдә”еҚҒеӣһеҝҢгҒ§жі•иҰҒгҒ®з· гӮҒгҒҸгҒҸгӮҠ(еј”гҒ„дёҠгҒ’)гҒЁгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
зҘҘжңҲе‘Ҫж—Ҙ(гҒ—гӮҮгҒҶгҒӨгҒҚгӮҒгҒ„гҒ«гҒЎ)гҒ®дҫӣйӨҠ
зҘҘжңҲе‘Ҫж—ҘгҒЁгҒҜгҖҒдәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹдәәгҒ®дёҖе‘ЁеҝҢд»ҘеҫҢгҒ«е·ЎгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢжӯ»дәЎжңҲ(зҘҘжңҲ)гҒ®жӯ»дәЎж—Ҙ(е‘Ҫж—Ҙ)гӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢиЁҖи‘үгҒ§гҖҒеҝҢж—ҘгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
3жңҲ15ж—ҘгҒ«дәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒҜгҖҒзҝҢе№ҙд»ҘйҷҚгҒ®3жңҲ15ж—ҘгҒҢзҘҘжңҲе‘Ҫж—ҘгҒ«гҒӮгҒҹгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ®гҒӘгҒӢгҒ«гҒҜгҖҒжҜҺе№ҙгҖҒж•…дәәгҒ®зҘҘжңҲе‘Ҫж—ҘгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰдҫӣйӨҠгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
зҘҘжңҲе‘Ҫж—ҘгҒ®дҫӣйӨҠгҒҜгҖҒж•…дәәгҒ«жғігҒ„гӮ’еҜ„гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶдҫӣйӨҠгҒ§гҒҷгҖӮ
жі•иҰҒгҒ«ж•…дәәгҒЁиҰӘгҒ—гҒ„еҸӢдәәгӮ„иҰӘжҲҡгӮ’жӢӣгҒ„гҒҰгҖҒгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«иӘӯзөҢгӮ’гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒиӘӯзөҢгҒ—гҒҹгҒӮгҒЁгҒ«дјҡйЈҹгӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
жңҲе‘Ҫж—ҘгҒ®дҫӣйӨҠ
жңҲе‘Ҫж—ҘгҒЁгҒҜгҖҒж•…дәәгҒҢдәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹж—ҘгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢиЁҖи‘үгҒ§гҒҷгҖӮе‘Ҫж—ҘгҒҢгҒӮгӮӢжңҲгӮ’гҒ®гҒһгҒҚгҖҒжҜҺжңҲгҒӮгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
3жңҲ15ж—ҘгҒ«дәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒҜгҖҒ3жңҲгӮ’йҷӨгҒ„гҒҹжҜҺжңҲ15ж—ҘгҒҢжңҲе‘Ҫж—ҘгҒ§гҒҷгҖӮжңҲе‘Ҫж—ҘгҒҜе№ҙгҒ«11еӣһгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жңҲе‘Ҫж—ҘгҒ®дҫӣйӨҠгҒҜгҖҒзҘҘжңҲе‘Ҫж—ҘгҒ®дҫӣйӨҠгҒЁгҒҠгҒӘгҒҳгҒ§ж•…дәәгҒ«жғігҒ„гӮ’еҜ„гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶдҫӣйӨҠгҒ§гҒҷгҖӮ
жүӢеҺҡгҒҸдҫӣйӨҠгӮ’гҒ—гҒҹгҒ„гҒӢгҒҹгҒҜгҖҒжңҲе‘Ҫж—ҘгҒ®дҫӣйӨҠгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢеҜәйҷўгғ»йңҠең’гӮ’жҺўгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
жҜҺжңҲ1еӣһгғ»жҜҺж—ҘгҒ®дҫӣйӨҠ
жңҲе‘Ҫж—ҘгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжҜҺжңҲ1еӣһгҖҒжұәгӮҒгӮүгӮҢгҒҹж—ҘгҒ«еҗҲеҗҢгҒ§дҫӣйӨҠгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒжҜҺж—Ҙж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гғ»зҙҚйӘЁе Ӯгғ»жЁ№жңЁи‘¬гҒ®гҒҫгҒҲгҒ§иӘӯзөҢгӮ’гҒҷгӮӢеҜәйҷўгғ»йңҠең’гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ—гҒҹеҫҢгҒ«еҲқзӣҶ(ж–°зӣҶ)гӮ„жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶж„Ҹе‘ігӮ„еҝ…иҰҒжҖ§
еҲқзӣҶ(ж–°зӣҶ)гӮ„жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶж„Ҹе‘і
жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶгҒЁж•…дәәгӮ’жҮҗгҒӢгҒ—гҒ„ж°—жҢҒгҒЎгҒ§жҖқгҒ„еҮәгҒҷж©ҹдјҡгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒйҒәж—ҸгӮ„иҰӘж—ҸгҒҢж°—жҢҒгҒЎгӮ’ж•ҙзҗҶгҒ§гҒҚгӮӢе ҙгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
д»Ҹж•ҷгҒ«гҒҜгҖҒгҒ”йҒәж—Ҹгғ»иҰӘж—Ҹгғ»ж•…дәәгҒ®з”ҹеүҚгҒ®еҸӢдәәзӯүж®ӢгҒ•гӮҢгҒҹдәәгҒҢжі•дәӢгғ»жі•иҰҒгӮ„гҒҠеў“еҸӮгӮҠгӮ’гҒҷгӮӢ(иҝҪе–„дҫӣйӨҠ)гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒж•…дәәгҒҢжҲҗд»ҸгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲж–№гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеҲқзӣҶ(ж–°зӣҶ)гӮ„жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶж„Ҹе‘ігҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҠеқҠгҒ•гӮ“гӮ’е‘јгӮ“гҒ§жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгӮ’гҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгӮӮгҖҒйҒәж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸгҖҒж•…дәәгҒ®з”ҹеүҚгҒ®еҸӢдәәгҒ§йӣҶгҒҫгҒЈгҒҰиҝ‘жіҒе ұе‘ҠгӮ’гҒ—гҒҰгҒҠеў“еҸӮгӮҠгӮ’гҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҖҒж•…дәәгҒ®иҝҪе–„дҫӣйӨҠгҒ«гӮӮгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ«йӣҶгҒҫгҒЈгҒҰжі•иҰҒгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ§еҲқзӣҶ(ж–°зӣҶ)гӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶгҒӢгҒҜиҮӘз”ұ
еҲқзӣҶгҒЁгҒҜгҖҒж•…дәәгҒҢдәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰеӣӣеҚҒд№қж—ҘгҒҢйҒҺгҒҺгҒҹгҒӮгҒЁгҖҒеҲқгӮҒгҒҰиҝҺгҒҲгӮӢгҒҠзӣҶгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒең°еҹҹгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜж–°зӣҶ(гҒ«гҒ„гҒјгӮ“)гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҲқзӣҶгҒ§гҒҜгҖҒйҒәж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸгҖҒж•…дәәгҒ®з”ҹеүҚгҒ®еҸӢдәәгӮ’йӣҶгӮҒгҒҰгҖҒгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«гӮҲгӮӢиӘӯзөҢгҖҒгҒ”з„јйҰҷгҖҒгҒҠеў“еҸӮгӮҠгҖҒзІҫйҖІж–ҷзҗҶгҒ®гӮӮгҒҰгҒӘгҒ—гӮ’гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еҲқзӣҶгҒҜгҖҒгҒҠеў“гӮ„иҮӘе®…гҒ®д»ҸеЈҮгҒ®жҺғйҷӨгӮ„зӣҶжЈҡгӮ„зӣҶжҸҗзҒҜгҒ®иЈ…йЈҫгҖҒ家ж—ҸгӮ„иҰӘжҲҡгҒ§йӣҶгҒҫгҒЈгҒҰгҒҠеў“еҸӮгӮҠгғ»д»ҸеЈҮгҒёгҒ®гҒҠдҫӣгҒҲгӮ’гҒҷгӮӢгҒҠзӣҶгҒ«гҒҸгӮҸгҒҲгҒҰгҖҒиӘӯзөҢгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ®жүӢй…ҚгҖҒзІҫйҖІж–ҷзҗҶгӮ’гӮӮгҒҰгҒӘгҒҷдјҡйЈҹе ҙжүҖгҒ®дәҲзҙ„гҖҒ家ж—ҸгӮ„иҰӘжҲҡгҒ®ж—ҘзЁӢиӘҝж•ҙгӮ’гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒжҷӮй–“гҒЁеҠҙеҠӣгҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ»гҒӢгҒ®жі•иҰҒгҒЁгҒҠгҒӘгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒ家ж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸеҒҙгҒ§еҲқзӣҶгҒ®жі•иҰҒгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒ„гҒҹгҒ„гғ»гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҹгӮүгҖҒжӨңиЁҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ§еҲқзӣҶ(ж–°зӣҶ)гӮ„жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶжіЁж„ҸзӮ№
еҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒёгҒҜж—©гӮҒгҒ«йҖЈзөЎгҒҷгӮӢ
гҒҠзӣҶгҒ®жҷӮжңҹгҒҜгҖҒеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰдёҖе№ҙгҒ®гҒҶгҒЎгҒ§гӮӮгҒЈгҒЁгӮӮеҝҷгҒ—гҒ„жҷӮжңҹгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒеҲқзӣҶгҒ®жі•иҰҒгӮ’гҒҷгӮӢгҒЁжұәгӮҒгҒҹгӮүгҖҒж—©гӮҒгҒ«еҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒёйҖЈзөЎгӮ’е…ҘгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§дәӢгҒ§гҒҷгҖӮ
жі•иҰҒгҒ«еҸӮеҲ—гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҒҹгҒ„дәәгҒҹгҒЎгҒ«гӮӮгҖҒгҒӘгӮӢгҒ№гҒҸж—©гҒҸйҖЈзөЎгӮ’е…ҘгӮҢгҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
дәӢеүҚгҒ«жү“гҒЎеҗҲгӮҸгҒӣгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸ
еҲқзӣҶгҒ§гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶжі•иҰҒгҒ®еҶ…е®№гғ»гҒ—гҒҚгҒҹгӮҠгҒ«гҒҜгҖҒе®—жҙҫгӮ„ең°еҹҹгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰйҒ•гҒ„гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮүгҖҒдәӢеүҚгҒ«еҜәйҷўгҒ«зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
жі•иҰҒеҪ“ж—ҘгҒ®жөҒгӮҢгҒҜгҖҒеүҚгӮӮгҒЈгҒҰжі•иҰҒгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶеҜәйҷўгғ»йңҠең’гӮ„дјҡйЈҹгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶж–ҷдәӯгғ»гғ¬гӮ№гғҲгғ©гғігҒЁжү“гҒЎеҗҲгӮҸгҒӣгӮ’гҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒе®үеҝғгҒ—гҒҰжі•иҰҒеҪ“ж—ҘгӮ’иҝҺгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
дҪ•еӣһеҝҢгҒҫгҒ§жі•иҰҒгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶгҒ№гҒҚгҒӢ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®жі•иҰҒгӮ’дҪ•еӣһеҝҢгҒҫгҒ§гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶгҒ№гҒҚгҒӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒең°еҹҹгӮ„еҖӢдәәгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘиҖғгҒҲж–№гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒдёғеӣһеҝҢгҖҒеҚҒдёүеӣһеҝҢгҒЁзҜҖзӣ®гҒ”гҒЁгҒ«гҖҒзҙ°гҒӢгҒҸжі•иҰҒгӮ’гҒҷгӮӢгҒӢгҒҹгӮӮгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдёүеӣһеҝҢгҒҫгҒ§гҒҠгҒ“гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒҹгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒҜгҖҒдҫӣйӨҠгғ»жі•иҰҒгӮ’ж–ҪиЁӯеҒҙгҒ«д»»гҒӣгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒиҰӘж—Ҹгғ»е®¶ж—ҸгҒЁи©ұгҒ—еҗҲгҒЈгҒҰеҝ…иҰҒгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒгҒқгӮҢд»ҘйҷҚгҒ®жі•иҰҒгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜж–ҪиЁӯеҒҙгҒ«гҒҠд»»гҒӣгҒ—гҒҰгӮӮгҒ„гҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
жі•иҰҒгҒ«гҒҜиӘ°гӮ’жӢӣеҫ…гҒҷгӮӢгҒ№гҒҚгҒӢ
гҒҠеў“еҸӮгӮҠгӮ„гҒҠеў“жҺғйҷӨгҖҒдҫӣйӨҠгӮ’еҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ«д»»гҒӣгӮӢж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ«жҠөжҠ—гҒҢгҒӮгӮӢдәәгҒҢгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®жі•иҰҒгҒҜгҖҒйҒәж—Ҹгғ»е®¶ж—Ҹгғ»ж•…дәәгҒ®з”ҹеүҚгҒ®иҰӘгҒ—гҒ„еҸӢдәәгҒӘгҒ©гҖҒж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®дҫӣйӨҠж–№жі•гӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒҹгҒ®гҒҝгӮ’жӢӣеҫ…гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ§гҒҷгҖӮ
жӢӣеҫ…гҒҷгӮӢдәәж•°гҒҢеў—гҒҲгӮӢгҒЁиІ»з”ЁгҒ®иІ жӢ…гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгӮӢгҖҒеҜәйҷўгғ»йңҠең’гӮ„дјҡйЈҹдјҡе ҙгҒЁгҒ®иӘҝж•ҙгҒҢиӨҮйӣ‘гҒ«гҒӘгӮӢгҒӘгҒ©е–Әдё»гҒ®иІ жӢ…гҒҢеў—гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҖҖ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ—гҒҹеҫҢгҒ®жі•иҰҒгҒ®жөҒгӮҢгҒЁжңҚиЈ…гҒЁгҒҠеёғж–ҪгҒ®зӣёе ҙ
- жі•иҰҒгҒ®жөҒгӮҢ
- ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®еҖӢеҲҘжі•иҰҒгҒ®жөҒгӮҢ
- ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒ®жңҚиЈ…
- ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®жі•иҰҒгҒ®еЎ”е©Ҷ
- жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒ®гҒҠеҜә(жң¬е°Ҡ)гҒёгҒ®гҒҠдҫӣгҒҲзү©гҒ®жёЎгҒ—ж–№
- жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒ®гҒҠеёғж–ҪгҒ®зӣёе ҙ
- жі•иҰҒгҒ§гҒҠеёғж–Ҫд»ҘеӨ–гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢиІ»з”Ё
жі•иҰҒгҒ®жөҒгӮҢ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гғ»жЁ№жңЁи‘¬гғ»зҙҚйӘЁе ӮгӮ’з®ЎзҗҶгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒҢгҒҫгҒЁгӮҒгҒҰгҒҠгҒ“гҒӘгҒҶжҳҘгғ»з§ӢгҒ®гҒҠеҪјеІёгҒ®жі•иҰҒгҖҒе№ҙеҝҢжі•иҰҒгӮ„зҘҘжңҲе‘Ҫж—ҘгҒ®жі•иҰҒгҒҜгҖҒиҰӘж—Ҹгғ»йҒәж—ҸгҒҢжә–еӮҷгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒеҖӢеҲҘжі•иҰҒгӮ’еёҢжңӣгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜ家ж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸгҒ§гҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«жі•иҰҒгӮ’дҫқй јгҒҷгӮӢгҖҒдјҡйЈҹгҒ®дјҡе ҙгҒ®жүӢй…ҚгӮ’гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®еҖӢеҲҘжі•иҰҒгҒ®жөҒгӮҢ
1. 家ж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸгҒЁж—ҘзЁӢгҒ®зӣёи«ҮгҖҒеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒЁгӮӮжі•иҰҒгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзӣёи«ҮгҒҷгӮӢ
家ж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸгӮ„ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠе…ҲгҒ®еҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ«жі•иҰҒгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзӣёи«ҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮжі•иҰҒгӮ’гӮ№гғ гғјгӮәгҒ«гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒ家ж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸгҒЁи©ұгҒ—еҗҲгҒЈгҒҰж—ҘзЁӢгӮ’зӣёи«ҮгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§дәӢгҒ§гҒҷгҖӮ
жң¬е ӮгҒ®дҪҝз”ЁгҖҒз”іиҫјгҒҝгҒ®з· еҲҮж—ҘгҖҒгҒҠдҫӣгҒҲгҖҒжі•иҰҒгҒ—гҒҹгҒӮгҒЁгҒ«гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶйЈҹдәӢдјҡ(гҒҠж–Һ)гҒӘгҒ©жі•иҰҒгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиҰҸеүҮгҒҜеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒЎгҒҢгҒҶгҒ®гҒ§гҖҒдәӢеүҚгҒ«зўәиӘҚгӮ’гҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒЁе®үеҝғгҒ§гҒҷгҖӮ
2. зҙҚйӘЁе…ҲгҒ®еҜәйҷўгҒ«жі•иҰҒгӮ’дҫқй јгҖӮгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜгҖҒиҮӘеҲҶгҒ§еғ§дҫ¶гӮ’жүӢй…ҚгҒҷгӮӢ
еҜәйҷўгҒ«зҙҚйӘЁгӮ’гҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒҜгҖҒеҜәйҷўгҒ®гҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«жі•иҰҒгӮ’дҫқй јгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
е…¬е–¶йңҠең’гӮ„ж°‘е–¶йңҠең’гҒ«зҙҚйӘЁгӮ’гҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒҜгҖҒйңҠең’гҒ«жҢҮе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«дҫқй јгҒҷгӮӢгҖҒгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜиҮӘеҲҶгҒ§гҒҠеқҠгҒ•гӮ“гӮ’жүӢй…ҚгҒ—гҒҰжі•иҰҒгӮ’дҫқй јгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
иҮӘеҲҶгҒ§гҒҠеқҠгҒ•гӮ“гӮ’жүӢй…ҚгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ®жҙҫйҒЈгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒиІ»з”ЁгӮ„еҜҫеҝңгӮЁгғӘгӮўгҒҢгҒЎгҒҢгҒҶгҒ®гҒ§гҖҒжҜ”ијғжӨңиЁҺгӮ’гҒ—гҒҰгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’йҒёгҒ¶гҒ“гҒЁгҒҢгҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ§гҒҷгҖӮ
3. жі•иҰҒеҪ“ж—Ҙ
жі•иҰҒеҪ“ж—ҘгҒҜгҖҒгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«гӮҲгӮӢиӘӯзөҢгҖҒгҒ”з„јйҰҷгӮ’гҒ—гҒҰзҙҚйӘЁгҒ—гҒҹгҒ”йҒәйӘЁгҒ®з®ЎзҗҶе ҙжүҖгҒ®гҒҫгҒҲгҒ§жүӢгӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгҒҫгҒҷгҖӮйҒәж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸгҒ®еёҢжңӣгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°дјҡйЈҹгӮӮгҒҠгҒ“гҒӘгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жі•иҰҒгӮ„дјҡйЈҹгҒҜ家ж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸгҒ®зөҶгӮ’ж·ұгӮҒгӮӢж©ҹдјҡгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеҲқзӣҶгғ»1еӣһеҝҢгғ»3еӣһеҝҢгҒӘгҒ©еӣһж•°гӮ’жұәгӮҒгҒҰдјҡйЈҹгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзӣёи«ҮиҖ…ж§ҳгӮӮгҒ„гӮүгҒЈгҒ—гӮғгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®жі•иҰҒгҒҜгҖҒеҖӢеҲҘжі•иҰҒгӮҲгӮҠ家ж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸгҒҢйЎ”гӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгӮӢжі•иҰҒгҒ®еӣһж•°гҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгӮӢеӮҫеҗ‘гҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒиҰӘж—Ҹгғ»йҒәж—ҸгҒЁи©ұгҒ—еҗҲгҒЈгҒҰжұәгӮҒгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠд»ҘеӨ–гҒ«иҮӘе®…гҒ®жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒ«еҜҫеҝңгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢзҙҚйӘЁе…ҲгӮӮгҒӮгӮӢ
ж•…дәәгҒҢдҪҸгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹйҰҙжҹ“гҒҝгҒҢгҒӮгӮӢе ҙжүҖгҒ§иҗҪгҒЎзқҖгҒ„гҒҰдҫӣйӨҠгҒ§гҒҚгӮӢгҖҒдјҡе ҙгғ»з§»еӢ•гғ»дјҡйЈҹгҒ®иІ»з”ЁгӮ’жҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒдёҖе‘ЁеҝҢгӮ„еӣӣеҚҒд№қж—ҘгҒ®дјҡе ҙгҒЁгҒ—гҒҰиҮӘе®…гӮ’йҒёгҒ¶гҒӢгҒҹгӮӮгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®дҫӣйӨҠж–№жі•гҒҜеҜәйҷўгғ»йңҠең’еҶ…гҒ«зҙҚйӘЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж•…дәәгӮ’гҒҫгҒЁгӮҒгҒҰдҫӣйӨҠгҒҷгӮӢеҗҲеҗҢжі•иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒзҙҚйӘЁе…ҲгҒ®гҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«еҖӢеҲҘжі•иҰҒгӮ’гҒҠйЎҳгҒ„гҒ§гҒҚгӮӢгҒӢзўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
иҮӘе®…гҒ®жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒҜгҖҒиӘӯзөҢж–ҷгҖҒгҒҠи»Ҡд»ЈгҖҒеҫЎиҶіж–ҷгҖҒгҒҠеҝғгҒҘгҒ‘гҖҒгҒҠеёғж–ҪгҖҒдјҡйЈҹиІ»гҖҒгҒҠдҫӣгҒҲгҖҒиҝ”зӨје“ҒгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹиІ»з”ЁгӮ„гҖҒд»ҸеЈҮгҒ®жә–еӮҷгҖҒгҒҠеҜәгҒёгҒ®зӣёи«ҮгҖҒж—ҘзЁӢиӘҝж•ҙгҖҒиҰӘж—Ҹгғ»йҒәж—ҸгҒёгҒ®е‘ЁзҹҘгҖҒж–ҷзҗҶгҒ®жүӢй…ҚгҖҒжЎҲеҶ…зҠ¶гҒ®жүӢй…ҚгҒӘгҒ©жҷӮй–“гҒҢгҒӢгҒӢгӮӢгҒ®гҒ§еүҚгӮӮгҒЈгҒҰжә–еӮҷгҒ—гҒҹгҒ»гҒҶгҒҢгҒ„гҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒ®жңҚиЈ…
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®жі•иҰҒгҒ®жңҚиЈ…гҒ«гҒҜгҖҒгҒЁгҒҸгҒ«жұәгҒҫгӮҠгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
йҒәж—Ҹгғ»иҰӘж—Ҹгғ»ж•…дәәгҒ®з”ҹеүҚгҒ®иҰӘгҒ—гҒ„еҸӢдәәгҒӘгҒ©гҒ§жі•иҰҒгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒз§ҒжңҚгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜгҖҒз”·жҖ§гҒӘгӮүй»’гғ»зҙәгғ»гӮ°гғ¬гғјгҒ®гӮ№гғјгғ„гҖҒеҘіжҖ§гҒӘгӮүй»’гҒ„гғ–гғ©гӮҰгӮ№гӮ„гӮ№гӮ«гғјгғҲгҒ«й»’гӮӮгҒ—гҒҸгҒҜгғҷгғјгӮёгғҘгҒ®гӮ№гғҲгғғгӮӯгғігӮ°(з•ҘејҸжӯЈиЈ…)гҒ§е•ҸйЎҢгҒӘгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
жҙҫжүӢгҒӘжңҚиЈ…гӮ„гғҺгғјгӮ№гғӘгғјгғ–гғ»гӮҝгғігӮҜгғҲгғғгғ—гғ»гғҸгғјгғ•гғ‘гғігғ„гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹиӮҢгҒ®йңІеҮәгҒҢеӨҡгҒ„жңҚиЈ…гҒҜйҒҝгҒ‘гҒҹгҒ»гҒҶгҒҢгҒ„гҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
ж•…дәәгҒ®жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒ«еҸӮеҲ—гҒҷгӮӢиҒ·е ҙгҒ®еҗҢеғҡгӮ„еҸӢдәәгҒ®жңҚиЈ…
ж•…дәәгҒ®иҰӘж—Ҹгғ»йҒәж—ҸгҒӢгӮүжңҚиЈ…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰжҢҮе®ҡгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°еҫ“гҒ„гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮжңҚиЈ…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰжҢҮе®ҡгҒҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒз•ҘејҸжӯЈиЈ…гҒ§еҸӮеҲ—гҒҷгӮӢгҒ®гҒҢз„ЎйӣЈгҒ§гҒҷгҖӮ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®жі•иҰҒгҒ®еЎ”е©Ҷ
иҸ©жҸҗеҜәгҒ®гҒҠеў“гҒ§гҒҜгҖҒжі•иҰҒгӮ„гҒҠеў“еҸӮгӮҠгӮ’гҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«гҒҠзөҢгҒ®ж–Үз« гӮ„ж–ҮеҸҘ(зөҢж–Ү)гӮ’жӣёгҒ„гҒҹеЎ”гҒ®еҪўгҒ®зёҰй•·гҒ®жңЁзүҮ(еЎ”е©Ҷ)гӮ’гҒҠеў“гҒ®еҫҢгӮҚгҒ«з«ӢгҒҰгҒҰгҖҒж•…дәәгҒ®еҶҘзҰҸгӮ’зҘҲгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ§гҒҜгҖҒеҜәйҷўгғ»йңҠең’гӮ„гҒ”йҒәйӘЁгӮ’з®ЎзҗҶгҒҷгӮӢе ҙжүҖгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒеЎ”е©ҶгӮ’е»әгҒҰгӮүгӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒ®гҒҠеҜә(жң¬е°Ҡ)гҒёгҒ®гҒҠдҫӣгҒҲзү©гҒ®жёЎгҒ—ж–№
еҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ§жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгӮ’гҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒгҒ”жң¬е°ҠгҒёгҒҠдҫӣгҒҲгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
еӢқжүӢгҒ«д»ҸеЈҮгҒ«гҒҠдҫӣгҒҲгӮ’гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҒҰгҖҒ гҒ”йҒәж—ҸгҒёгҒ®гҒ”жҢЁжӢ¶гҒ§жёЎгҒҷгҖҒгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜж–Ҫдё»гҒ®дәҶжүҝгӮ’еҫ—гҒҰд»ҸеЈҮгҒ«гҒҠдҫӣгҒҲгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒ”йҒәж—ҸгҒёгҒ”жҢЁжӢ¶гҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒпҪўжң¬ж—ҘгҒҜгҒҠжӢӣгҒҚгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒЎгӮүгӮ’еҫЎд»ҸеүҚгҒ«гҒҠдҫӣгҒҲгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮпҪЈгҒӘгҒ©дёҖиЁҖж·»гҒҲгҒҰгҖҒдёӯиә«гӮ’гҒ гҒ—гҒҰгҒҠжёЎгҒ—гҒҷгӮӢгҒ®гҒҢгғһгғҠгғјгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҠдҫӣгҒҲзү©гҒ®жҺӣгҒ‘зҙҷгҒ®йҒёгҒіж–№
жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒ®гҒҠдҫӣгҒҲзү©гҒ®з®ұгҒ«гҒҜгҖҒзҘқгҒ„гҒ”гҒЁиҙҲзү©гҒЁгҒ—гҒҰдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢзҶЁж–—зҙҷ(гҒ®гҒ—гҒҢгҒҝ)гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҒҰжҺӣгҒ‘зҙҷ(гҒӢгҒ‘гҒҢгҒҝ)гӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
ж°ҙеј•(йЈҫгӮҠзҙҗ)гҒ®еҪўгҒҜзөҗгҒіеҲҮгӮҠгҒ§гҖҒиүІгҒҜеӣӣеҚҒд№қж—ҘгҒҫгҒ§гҒҜзҷҪй»’гҖҒгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜеҸҢйҠҖгҒҢдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢеҹәжң¬гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒиҘҝж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜй»„иүІгҒЁзҷҪиүІгӮ’дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жҺӣгҒ‘зҙҷгҒ«иЁҳијүгҒҷгӮӢиЎЁжӣёгҒҚгҒҜгҖҒгҒҠдҫӣгҒҲзү©гӮ’гҒҠжёЎгҒ—гҒҷгӮӢгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гӮ„ең°еҹҹгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒЎгҒҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еӣӣеҚҒд№қж—Ҙжі•иҰҒгӮҲгӮҠеүҚгҒҜпҪўеҫЎйңҠеүҚпҪЈгҖҒеӣӣеҚҒд№қж—Ҙжі•иҰҒгӮҲгӮҠгҒӮгҒЁгҒҜпҪўеҫЎд»ҸеүҚпҪЈпҪўеҫЎдҪӣеүҚпҪЈгҖҒж–°зӣҶгҒҜпҪўж–°зӣҶеҫЎиҰӢиҲһпҪЈгҒЁиЁҳијүгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
жө„еңҹзңҹе®—гҒҜдәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒӮгҒЁгҒҜд»Ҹж§ҳгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеӣӣеҚҒд№қж—Ҙжі•иҰҒгӮҲгӮҠеүҚгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮпҪўеҫЎд»ҸеүҚпҪЈгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮеҗҚеҸӨеұӢеёӮеҶ…гҒ§гҒҜгҒҠдҫӣгҒҲзү©гӮ’гҒҠжёЎгҒ—гҒҷгӮӢгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒ«гҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгӮӮпҪўеҫЎдҫӣпҪЈгӮ’дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҠдҫӣгҒҲзү©гҒ®жҺӣгҒ‘зҙҷгҒ®гҒӢгҒ‘гҒӢгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҶ…еҒҙгҒ«гҒӢгҒ‘гӮӢж–№жі•гҒЁеӨ–еҒҙгҒ«гҒӢгҒ‘гӮӢж–№жі•гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ©гҒЎгӮүгҒҢгҒ„гҒ„гҒӢжұәгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮжі•иҰҒгҒ«еҮәеёӯгҒҷгӮӢгҒӘгӮүеӨ–еҒҙгҒ«гҖҒеҮәеёӯгҒ—гҒӘгҒ„гҒӘгӮүеҶ…еҒҙгҒ«гҒӢгҒ‘гӮӢгҒӢгҒҹгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгӮ’ж¬ еёӯгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«гҒҠдҫӣгҒҲзү©гӮ’йҖҒгӮӢгҒЁгҒҚгҒ®гғһгғҠгғј
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒ«гҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒЁгҒҚгҖҒдҪ“иӘҝдёҚиүҜгғ»еҰҠеЁ дёӯгҒӘгҒ©гӮ„гӮҖгӮ’еҫ—гҒӘгҒ„зҗҶз”ұгҒҢгҒӮгӮӢгҒӘгӮүж¬ еёӯгҒ—гҒҰе·®гҒ—ж”ҜгҒҲгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгӮ’ж¬ еёӯгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒгҒ”йҒәж—ҸгҒ«еҮәеёӯгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ„гҒҠдҫӣгҒҲзү©гӮ’йҖҒгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠдјқгҒҲгҒҷгӮӢгҒЁгӮҲгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒҠдҫӣгҒҲзү©гӮ„йҰҷе…ёгҒҜжі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒ®2пҪһ3ж—ҘеүҚгҒ«гҒ”йҒәж—ҸгҒ®гӮӮгҒЁгҒёеұҠгҒҸгӮҲгҒҶжүӢй…ҚгҒҷгӮӢгҒЁиҰӘеҲҮгҒ§гҒҷгҖӮ
жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒ®гҒҠеёғж–ҪгҒ®зӣёе ҙ
гҒҠеёғж–ҪгҒЁиІ»з”ЁгҒ®гҒЎгҒҢгҒ„
гҒҠеёғж–ҪгҒҜгҖҒиӘӯзөҢгӮ’иӘӯгӮ“гҒ§гӮӮгӮүгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒжҲ’еҗҚгӮ’гҒӨгҒ‘гҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҹгҒҠзӨјгғ»еҜҫдҫЎгҒЁгҒ—гҒҰгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«жёЎгҒҷйҮ‘йҠӯгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§жҚүгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжң¬жқҘгҒ®ж„Ҹе‘ігҒҜгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒёгҒ®гҒҠзӨјгғ»еҜҫдҫЎгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҒҰгҖҒжң¬е°ҠгҒ§гҒӮгӮӢд»Ҹж§ҳгҒ«гҒҠдҫӣгҒҲгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒ”жң¬е°ҠгӮ’гҒҠе®ҲгӮҠгҒҷгӮӢеҜәйҷўгҒ®з¶ӯжҢҒгғ»жҙ»еӢ•иІ»гҒ«гҒӮгҒҰгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҠеёғж–ҪгҒ®зӣёе ҙгҒЁзӣ®е®ү
гҒҠеёғж–ҪгҒҜгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§гҖҒгҒ”жң¬е°ҠгҒёгҒ®гҒҠдҫӣгҒҲгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒж°ёд»ЈдҫӣйӨҠж–ҷгӮ„еҲ»еӯ—ж–ҷгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«йҮ‘йЎҚгҒҢжұәгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ3дёҮеҶҶпҪһ5дёҮеҶҶгӮ’гҒҠеҢ…гҒҝгҒ—гҒҰгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«жёЎгҒҷгҒӢгҒҹгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ©гӮҢгҒҸгӮүгҒ„гҒ®йҮ‘йЎҚгӮ’гҒҠж”Ҝжү•гҒ„гҒҷгӮӢгҒ№гҒҚгҒӢж°—гҒ«гҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒпҪўгҒ„гҒҸгӮүеҢ…гӮҒгҒ°гҒ§гҒҷгҒӢпҪЈгҒЁе°ӢгҒӯгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҒҰгҖҒпҪўзҡҶгҒ•гӮ“гҒ©гӮҢгҒҸгӮүгҒ„гҒ®йҮ‘йЎҚгӮ’гҒҠеҢ…гҒҝгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҒӢпҪЈгҒЁгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«гҒҠиҒһгҒҚгҒҷгӮӢгҒЁж•ҷгҒҲгҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҠеёғж–ҪгҒ®йҮ‘йЎҚгҒ®зӣ®е®ү
| жі•иҰҒгҒ®зЁ®йЎһ | йҮ‘йЎҚгҒ®зӣ®е®ү |
|---|---|
| еӣӣеҚҒд№қж—Ҙ | 3пҪһ5дёҮеҶҶ |
| дёҖе‘ЁеҝҢ | 3пҪһ5дёҮеҶҶ |
| дёүеӣһеҝҢ | 1пҪһ5дёҮеҶҶ |
| дёғеӣһеҝҢ | 1пҪһ5дёҮеҶҶ |
жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒ®гҒҠеёғж–ҪгҒ®е…ҘгӮҢж–№гғ»жёЎгҒ—ж–№гҒЁжёЎгҒҷгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°
гҒҠеёғж–ҪгҒ®е…ҘгӮҢж–№
гҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒҢзҷҪе°Ғзӯ’гғ»дёӯеҢ…гҒҝгӮ’й–ӢгҒ‘гҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒиӮ–еғҸз”»гҒҢеҢ…гҒҝгҒ®дёҠеҒҙгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«е…ҘгӮҢгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮиӨҮж•°жһҡгҒҠжңӯгӮ’гҒ„гӮҢгӮӢгҒЁгҒҚгҒҜи§’гӮ’ж•ҙгҒҲгҒҰе…ҘгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҠеёғж–ҪгҒЁгҒ—гҒҰеҢ…гӮ“гҒ гҒҠжңӯгҒҜгҖҒж–°жңӯгӮ„дҪҝз”Ёй »еәҰгҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҒҠжңӯгӮ’дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҹәжң¬гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒж–°жңӯгӮ’дҪҝгӮҸгҒӘгҒ„ең°еҹҹгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒдәӢеүҚгҒ«иҰӘж—ҸгҒЁзӣёи«ҮгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒҠеёғж–ҪгҒ®иЎЁжӣёгҒҚгҒ®гғһгғҠгғј
гҒҠеёғж–ҪиўӢгҒ®иЎЁйқўгҒ®дёӯеӨ®гҒ®дёҠйғЁгҒ«пҪўгҒҠеёғж–ҪпҪЈпҪўеҫЎеёғж–ҪпҪЈпҪўеҫЎзӨјпҪЈгҒ®гҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгҖҒиЎЁйқўгҒ®дёӯеӨ®гҒ®дёӢйғЁгҒ«ж–Ҫдё»гҒ®еҗҚеүҚгӮ’гғ•гғ«гғҚгғјгғ гӮӮгҒ—гҒҸгҒҜ姓гҒ®гҒҝиЁҳијүгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҠеёғж–ҪиўӢгҒ®гҒӘгҒӢгҒ®зҷҪе°Ғзӯ’гғ»дёӯеҢ…гҒҝгҒ«гҒҜгҖҒеҢ…гӮ“гҒ йҮ‘йЎҚгҖҒдҪҸжүҖгҖҒйӣ»и©ұз•ӘеҸ·гӮ’иЁҳијүгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
зҷҪе°Ғзӯ’гғ»дёӯеҢ…гҒҝгҒҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒгҒҠеёғж–ҪиўӢгҒ®иЈҸйқўгҒ«гҖҒеҢ…гӮ“гҒ йҮ‘йЎҚгҖҒдҪҸжүҖгҖҒйӣ»и©ұз•ӘеҸ·гӮ’иЁҳијүгҒҷгӮӢгҒЁдёҒеҜ§гҒ§гҒҷгҖӮ
иЁҳијүгҒҜгҖҒзӯҶгғҡгғігҒӢй»’еўЁгҒ®зӯҶгӮ’дҪҝгҒҶгҒ®гҒҢгҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ§гҒҷгҖӮеҢ…гӮ“гҒ йҮ‘йЎҚгӮ’иЁҳијүгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒеЈұгҖҒејҗгҖҒеҸӮгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«ж—§еӯ—гҒ®жјўж•°еӯ—гӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҖҒпҪўд№ҹпҪЈгӮ’ж·»гҒҲгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒ3дёҮеҶҶгӮ’еҢ…гӮ“гҒ е ҙеҗҲгҒҜпҪўйҮ‘еҸӮиҗ¬ең“д№ҹпҪЈгҒЁиЁҳијүгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҠеёғж–ҪгҒ®жёЎгҒ—ж–№гҒЁжёЎгҒҷгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°
гҒҠеёғж–ҪгӮ’гҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«жёЎгҒҷгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒжүӢжёЎгҒ—гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҒҰгҖҒеҲҮжүӢзӣҶгҒЁгҒ„гҒҶе°ҸгҒ•гҒӘгҒҠзӣҶгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜгҖҒгҒөгҒҸгҒ•(иўұзҙ—)гҒ®гҒҶгҒҲгҒ«гҖҒгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒӢгӮүиҰӢгҒҰиӘӯгҒҝгӮ„гҒҷгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«дёҠдёӢйҖҶеҗ‘гҒҚгҒ§зҪ®гҒ„гҒҰжёЎгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҠеёғж–ҪгӮ’жёЎгҒҷгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒҜгҖҒжі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒҢзөӮгӮҸгҒЈгҒҰдёҖдј‘гҒҝгҒ—гҒҹгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒ§гҒҠжёЎгҒ—гҒҷгӮӢгҒ®гҒҢгҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ§гҒҷгҖӮ
жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒҢзөӮгӮҸгҒЈгҒҹгҒӮгҒЁгҒ«гҒҠжёЎгҒ—гҒҷгӮӢгҒ®гҒҢгӮҖгҒҡгҒӢгҒ—гҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒжі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒ®гҒҫгҒҲгҒ«гҖҒгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«жҢЁжӢ¶гҒҷгӮӢгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒ§гҒҠжёЎгҒ—гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
жі•иҰҒгҒ§гҒҠеёғж–Ҫд»ҘеӨ–гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢиІ»з”Ё
е ҙжүҖд»Ј
жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒ®дјҡе ҙгҖҒеҸӮеҠ гҒҷгӮӢдәәж•°гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒЎгҒҢгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдјҡе ҙгҒҢиҮӘе®…гҒӘгӮү0еҶҶгҖҒеҜәйҷўгҒ®жң¬е ӮгҒӘгӮү5еҚғеҶҶпҪһ2дёҮеҶҶзЁӢеәҰгҖҒж°‘й–“гҒ§йҒӢе–¶гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮ»гғ¬гғўгғӢгғјгғӣгғјгғ«гҒӘгӮү3дёҮеҶҶзЁӢеәҰгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҫЎи»Ҡд»Ј
иҮӘе®…гӮ„гӮ»гғ¬гғўгғӢгғјгғӣгғјгғ«гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒҢеҜәйҷўгҒӢгӮүгҒ»гҒӢгҒ®е ҙжүҖгҒёз§»еӢ•гҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢиІ»з”ЁгҒ§гҖҒ移еӢ•гҒҷгӮӢи·қйӣўгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒЎгҒҢгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒ3еҚғеҶҶ~1дёҮеҶҶзЁӢеәҰгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дјҡйЈҹд»Ј
жі•иҰҒгҒ«еҸӮеҲ—гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹгҒӢгҒҹгӮ’гҒҠгӮӮгҒҰгҒӘгҒ—гҒҷгӮӢдјҡйЈҹгҒ®д»ЈйҮ‘гҒ§гҖҒ1дәәгҒӮгҒҹгӮҠ3еҚғеҶҶпҪһ5еҚғеҶҶзЁӢеәҰгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҫЎиҶіж–ҷ
жі•иҰҒгҒ«еҸӮеҲ—гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹгҒӢгҒҹгӮ’гҒҠгӮӮгҒҰгҒӘгҒ—гҒҷгӮӢдјҡйЈҹгҒ«гҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒҢеҸӮеҠ гҒ—гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҖҒж„ҹи¬қгҒ®ж°—жҢҒгҒЎгӮ’иҫјгӮҒгҒҰгҒҠжёЎгҒ—гҒҷгӮӢиІ»з”ЁгҒ§гҖҒ5еҚғеҶҶпҪһ1дёҮеҶҶзЁӢеәҰгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ—гҒҹеҫҢгҒ®гҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒ®ж–№жі•гғ»гҒҠдҫӣгҒҲгғ»жңҚиЈ…гҒ®гғһгғҠгғј
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ§гӮӮгҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒҜгҒ§гҒҚгӮӢ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ§гӮӮгҖҒгҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒҜгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒж–ҪиЁӯгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢжҷӮй–“гҒҢжұәгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒдәӢеүҚгҒ«зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒ„гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
з®ЎзҗҶдәӢеӢҷжүҖгӮ„еҸ—д»ҳгҒҢгҒӮгӮӢеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒҜгҖҒгҒІгҒЁеЈ°гҒӢгҒ‘гҒҰгҒӢгӮүгҒҠеҸӮгӮҠгӮ’гҒҷгӮӢгҒ®гҒҢгғһгғҠгғјгҒ§гҒҷгҖӮ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гғ»жЁ№жңЁи‘¬гғ»зҙҚйӘЁе ӮгҒ®жҺғйҷӨгҒҜеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰеҝ…иҰҒгҒӘгҒ„
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒҜгҒ”йҒәйӘЁгӮ„ж•…дәәгҒ®дҫӣйӨҠгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҒҰгҖҒз®ЎзҗҶгӮӮж–ҪиЁӯеҒҙгҒ«гҒҠд»»гҒӣгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§жҺғйҷӨгҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒҢдёҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒдҫӢеӨ–гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒзҙҚйӘЁе…ҲгҒҢгғӯгғғгӮ«гғјеһӢгҒ®зҙҚйӘЁе ӮгҒ®е ҙеҗҲгҖҒеҖӢе®ӨеҶ…гҒ®жҺғйҷӨгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶеҝ…иҰҒжҖ§гҒҢеҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮеҖӢеҲҘгҒ«еў“зҹігӮ’е»әгҒҰгӮӢж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гҒ®гҒӘгҒӢгҒ«гҒҜгҖҒжҺғйҷӨгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ”йҒәж—ҸеҒҙгҒ§жҺғйҷӨгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ®гҒӢдёҚиҰҒгҒӘгҒ®гҒӢгҒҜгҖҒеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ«зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒ»гҒӢгҖҒз®ЎзҗҶж–ҷгҒ®гҒӘгҒӢгҒ«жҺғйҷӨгҒ®иІ»з”ЁгҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒҢгғқгӮӨгғігғҲгҒЁгҒ—гҒҰеҲӨж–ӯгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒ®жңҚиЈ…гҒ«жұәгҒҫгӮҠгҒҜгҒӘгҒ„
гҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒ®жңҚиЈ…гҒҜжі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒЁгҒҠгҒӘгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒжұәгҒҫгӮҠгҒҢгҒӮгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮд»•дәӢеё°гӮҠгҒ®гӮ№гғјгғ„гӮ„жҷ®ж®өзқҖгҒ§гҒҠеҸӮгӮҠгҒ«гҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒ«иЎҢгҒЈгҒҰгӮӮеӨ§дёҲеӨ«гҒ§гҒҷгҖӮ
жңҖдҪҺйҷҗгҒ®иә«гҒ гҒ—гҒӘгҒҝгӮ„жё…жҪ”ж„ҹгҒҜеӨ§дәӢгҒ«гҒ—гҒҹгҒ»гҒҶгҒҢгҒ„гҒ„гҒ®гҒ§гҖҒжұҡгӮҢгҒҢзӣ®з«ӢгҒӨжңҚиЈ…гӮ„гҒ гӮүгҒ—гҒӘгҒ„жңҚиЈ…гҒҜйҒҝгҒ‘гҒҰгҖҒзҜҖеәҰгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒ«иЎҢгҒҸгҒЁгҒ„гҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒҜгҒҠеёғж–ҪгӮ’жҢҒеҸӮгҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгӮҲгҒ„
жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒҜгҖҒгҒҠеёғж–ҪгӮ’жҢҒеҸӮгҒ—гҒҰгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«гҒҠжёЎгҒ—гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒ§гҒҜеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮеҝ…иҰҒгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒҠеў“еҸӮгӮҠгӮ’гҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«иӘӯзөҢгӮ’гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒгҒҠзӨј3еҚғеҶҶпҪһ1дёҮеҶҶзЁӢеәҰгҒ®иӘӯзөҢж–ҷ(дҫӣйӨҠж–ҷ)гӮ’гҒҠжёЎгҒ—гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒ®жөҒгӮҢ
еҜәйҷўеў“ең°гӮ„йңҠең’еў“ең°гҒҜгҖҒжүӢжЎ¶(гҒҰгҒҠгҒ‘)гӮ„жҹ„жқ“(гҒІгҒ—гӮғгҒҸ)гӮ„гҖҒдј‘жҶ©жүҖгҖҒгғҲгӮӨгғ¬гҖҒгҒҠиҠұгӮ„гҒҠз·ҡйҰҷгӮ’иіје…ҘгҒ§гҒҚгӮӢеЈІеә—гҒҢеӮҷгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒйӣҶиҗҪгҒ«гҒӮгӮӢе…ұеҗҢеў“ең°гҒ«гҒҜз”Ёж„ҸгҒ•гӮҢгҒҰгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒдәӢеүҚгҒ«жә–еӮҷгҒ—гҒҰжҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
еў“ең°гҒ«гҒӨгҒ„гҒҹгӮүгҖҒеҜәйҷўеў“ең°гҒӘгӮүжң¬е ӮгҒ®гҒ”жң¬е°ҠгҒ«гҒҠеҸӮгӮҠгҒ—гҒҹгҒ®гҒЎдҪҸиҒ·гҒ«жҢЁжӢ¶гҖҒйңҠең’еў“ең°гҒӘгӮүз®ЎзҗҶдәӢеӢҷжүҖгӮ„еў“ең°гҒ®з®ЎзҗҶдәәгҒ«жҢЁжӢ¶гҒ—гҒҰгҒӢгӮүгҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ”йҒәйӘЁгӮ’е®үзҪ®гҒҷгӮӢж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гҒ®зЁ®йЎһгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒЎгҒҢгҒҶгҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒ®ж–№жі•гӮ„гҒҠдҫӣгҒҲзү©гҒ®гғһгғҠгғј
е…ұйҖҡгҒ®гҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒ®ж–№жі•гӮ„гҒҠдҫӣгҒҲзү©гҒ®гғһгғҠгғј
еў“зҹігҒ®жҺғйҷӨгӮ’гҒҷгӮӢгҖҒгӮҚгҒҶгҒқгҒҸгӮ’з«ӢгҒҰгҒҰзҒ«гӮ’зҒҜгҒҷгҖҒгҒҠз·ҡйҰҷгҒ«зҒ«гӮ’зӮ№гҒ‘гҒҰз«ӢгҒҰгӮӢгҖҒгҒҠиҠұгӮ’дҫӣгҒҲгӮӢгҖҒж°ҙйүўгҒ«гҒҚгӮҢгҒ„гҒӘж°ҙгӮ’е…ҘгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжөҒгӮҢгҒҜгҖҒжҳ”гҒӢгӮүгҒҠгҒ“гҒӘгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒ®ж–№жі•гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҠдҫӣгҒҲзү©гӮ’гҒҠеў“гҒ®дёҠгҒ«зӣҙжҺҘзҪ®гҒӢгҒӘгҒ„гҖҒиўӢгӮ„з®ұгҒ«е…ҘгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒҜеҸЈгӮ’й–ӢгҒ‘гҒҰдҫӣгҒҲгӮӢгҖҒйЈІйЈҹзү©гҒҜгҒҠеў“гҒ«ж®ӢгҒ•гҒҡйЈҹгҒ№гӮӢгҖҒгғҠгғһгғўгғҺгҒҜйҒҝгҒ‘гӮӢгҖҒдә”иҫӣ(гҒӯгҒҺгғ»гҒ«гӮүгғ»гҒ«гӮ“гҒ«гҒҸгғ»гӮүгҒЈгҒҚгӮҮгҒҶгғ»гҒҜгҒҳгҒӢгҒҝ)гӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгғһгғҠгғјгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮжҳ”гҒӢгӮүгҒҠгҒӘгҒҳгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгҒ”еӯҳзҹҘгҒ®гҒӢгҒҹгҒҢеӨҡгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®гҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒ®ж–№жі•гӮ„гғһгғҠгғјгҒҜгҖҒгҒ”йҒәйӘЁгӮ’е®үзҪ®гҒҷгӮӢе ҙжүҖ(йӣҶеҗҲе®үзҪ®еһӢгҒ®ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гҖҒеҖӢеҲҘе®үзҪ®еһӢгҒ®ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гҖҒжЁ№жңЁи‘¬гҖҒзҙҚйӘЁе Ӯ)гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒЎгҒҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
йӣҶеҗҲе®үзҪ®еһӢгҒ®ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“
гҒ”йҒәйӘЁгӮ’гҒІгҒЁгҒӨгҒ®гӮ№гғҡгғјгӮ№гҒ«гҒҫгҒЁгӮҒгҒҰе®үзҪ®гҒҷгӮӢж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гҒҜгҖҒйӣҶеҗҲе®үзҪ®еһӢгҒ®ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гҒЁгӮҲгҒ°гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
йӣҶеҗҲе®үзҪ®еһӢгҒ®ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гҒҜгҖҒеӨ§гҒҚгҒӘйҰҷзӮүгӮ„дҫӣиҠұеҸ°гҒҢиЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮгҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒҜеӨ§гҒҚгҒӘйҰҷзӮүгҒ®гҒҫгҒҲгҒ§гҒҠз·ҡйҰҷгӮ’з„ҡгҒ„гҒҰжүӢгӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгҒҫгҒҷгҖӮ
еҖӢеҲҘе®үзҪ®еһӢгҒ®ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“
еҖӢеҲҘгҒ®гӮ№гғҡгғјгӮ№гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®гӮ№гғҡгғјгӮ№гҒ«гҒ”йҒәйӘЁгӮ’е®үзҪ®гҒҷгӮӢж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гҒҜеҖӢеҲҘе®үзҪ®еһӢгҒ®ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гҒЁгӮҲгҒ°гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҖӢеҲҘе®үзҪ®еһӢгҒ®ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гҒҜгҖҒеҖӢеҲҘгҒ®еў“зҹігӮ„ж•…дәәеҗҚгҒҢеҲ»еҚ°гҒ•гӮҢгҒҹгғ—гғ¬гғјгғҲгҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒж•…дәәгҒҢгҒ©гҒ“гҒ§зң гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒҢгҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒЁгӮҸгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒҜгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®гҒ”йҒәйӘЁгҒ®гӮ№гғҡгғјгӮ№гҒ®гҒҫгҒҲгҒ§гҒҠз·ҡйҰҷгӮ’з„ҡгҒ„гҒҰжүӢгӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгҒҫгҒҷгҖӮ
зҙҚйӘЁе Ӯ
зҙҚйӘЁе ӮгҒ«гҒҜгҖҒгғӯгғғгӮ«гғјеһӢзҙҚйӘЁе ӮгҖҒгҒ”жң¬е°ҠгӮ„дҪҚзүҢгӮ’зҪ®гҒҸгӮ№гғҡгғјгӮ№гҒЁйӘЁеЈәгӮ’е®үзҪ®гҒҷгӮӢгӮ№гғҡгғјгӮ№гҒҢгӮҸгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢйңҠе»ҹеһӢзҙҚйӘЁе ӮгҖҒгӮ«гғјгғүгҒ®е·®гҒ—иҫјгҒҝгӮ„гғңгӮҝгғігӮ’жҠјгҒҷгҒЁгҒ”йҒәйӘЁгҒҢеҸӮжӢқгӮ№гғҡгғјгӮ№гҒ«е‘јгҒіеҮәгҒ•гӮҢгӮӢиҮӘеӢ•жҗ¬йҖҒеһӢзҙҚйӘЁе ӮгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҖӢеҲҘгҒ«гҒҠдҫӣгҒҲзү©гӮ„гҒҠз·ҡйҰҷгӮ„иЁҳеҝөе“ҒгҒҢзҪ®гҒ‘гӮӢгҖҒе…ұеҗҢгҒ®йҰҷзӮүгӮ„дҫӣиҠұеҸ°гҒҢз”Ёж„ҸгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖҒзҙҚйӘЁе ӮеҶ…гҒ®жё…жҪ”гӮ’дҝқгҒӨгҒҹгӮҒгҒ«гҒҠиҠұгӮ„йЈҹгҒ№зү©гҖҒйЈІгҒҝзү©гҒӘгҒ©з”ҹгӮӮгҒ®гҒ®гҒҠдҫӣгҒҲгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖҒгӮўгғ«гӮігғјгғ«гҒ®жҢҒгҒЎиҫјгҒҝзҰҒжӯўгҖҒгҒҠзөҢгӮ’иӘӯгҒҝдёҠгҒ’зҰҒжӯўгҒӘгҒ©гҖҒзҙҚйӘЁе ӮгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиЁӯеӮҷгӮ„иҰҸеүҮгҒҜгҒЎгҒҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зҙҚйӘЁе ӮгҒ®гҒҠеҸӮгӮҠгҒҜдәҲзҙ„дёҚиҰҒгҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеӨңй–“гҒҜж–ҪйҢ гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒдәӢеүҚгҒ«еҸ—д»ҳжҷӮй–“гӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
йҖұжң«гӮ„гҒҠзӣҶгғ»гҒҠеҪјеІёгҖҒйҖЈдј‘гӮ„гҖҒжі•иҰҒгҒҢгҒҠгҒ“гҒӘгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁж··гҒҝеҗҲгҒҶеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҒ®гҒ§дәӢеүҚгҒ«з®ЎзҗҶдәӢеӢҷжүҖгҒ«е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ®гҒҢгҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ§гҒҷгҖӮ
жЁ№жңЁи‘¬
жЁ№жңЁи‘¬гҒ«гҒҜгҖҒйғҪеёӮйғЁгҒ«еӨҡгҒ„йңҠең’еһӢгҒ®жЁ№жңЁи‘¬гҖҒең°ж–№гҒ«еӨҡгҒ„гҒ”йҒәйӘЁгӮ’гҒқгҒ®гҒҫгҒҫеңҹдёӯгҒ«еҹӢ葬гҒҷгӮӢйҮҢеұұеһӢжЁ№жңЁи‘¬гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
йңҠең’еһӢгҒ®жЁ№жңЁи‘¬гҒҜгҖҒгғ—гғ¬гғјгғҲгҒ§ж•…дәәгҒҢзң гӮӢе ҙжүҖгӮ’зү№е®ҡгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгҒҠеҸӮгӮҠгҒ®гҒЁгҒҚгҒ«ж•…дәәгҒ®гҒҫгҒҲгҒ§жүӢгӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
йҮҢеұұеһӢжЁ№жңЁи‘¬гҒҜгҖҒгҒ©гҒ®жЁ№жңЁгҒ®гӮӮгҒЁгҒ«гҒ”йҒәйӘЁгҒҢеҹӢ葬гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢдёҖиҰӢгҒҷгӮӢгҒЁгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒзӣ®еҚ°гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҰгҒҠгҒҸгҒЁгҒ„гҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
еұұзҒ«дәӢйҳІжӯўгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒҠз·ҡйҰҷгӮ„гӮҚгҒҶгҒқгҒҸгӮ’жҢҒгҒЎиҫјгӮҒгҒӘгҒ„гҖҒгҒҠж°ҙгӮ’е…ҘгӮҢгҒҰиҠұ瓶гӮ’иЁӯзҪ®гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶиҰҸеүҮгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еұұеҘҘгҒ«гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒзҷ»еұұйқҙгӮ„жӯ©гҒҚгӮ„гҒҷгҒ„гӮ№гғӢгғјгӮ«гғјгӮ’еұҘгҒҸгҖҒж°ҙзӯ’гҒӘгҒ©ж°ҙеҲҶиЈңзөҰгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮӮгҒ®гӮ’жҢҒеҸӮгҒҷгӮӢгҖҒйӣЁгҒҢйҷҚгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢж—ҘгӮ„йўЁгҒҢеј·гҒ„ж—ҘгҒҜйҒҝгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮ
еў“ең°гҒ®з®ЎзҗҶиҖ…гҒҢй§…гӮ„й§җи»Ҡе ҙгҒӢгӮүйҖҒиҝҺгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒдәӢеүҚгҒ«иҰӢеӯҰдәҲзҙ„гӮ’гҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«зўәиӘҚгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
е–Ә家гҒ«е‘јгҒ°гӮҢгҒҰгҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒ«гҒ„гҒҸгҒЁгҒҚгҒ®гҒҠдҫӣгҒҲ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒиҰӘж—ҸгӮ„ж•…дәәгҒ®з”ҹеүҚгҒ®еҸӢдәәгҒЁгҒ—гҒҰгҒ”йҒәж—ҸгҒЁдёҖз·’гҒ«гҒҠеў“еҸӮгӮҠгӮ’гҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒгҒ”йҒәж—ҸгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰ3,000еҶҶ~5,000еҶҶзЁӢеәҰгӮ’зҷҪгҒЁй»’гҒ®ж°ҙеј•гҒҢгҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢйҰҷе…ёиўӢгҒ«е…ҘгӮҢгҒҰдҫӣгҒҲгӮӢгҒ®гҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҖӮ
жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгӮ’гҒ®гҒһгҒ„гҒҰгҒ”йҒәйӘЁгӮ’ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ—гҒҹеҫҢгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢиІ»з”Ё
- гҒ”йҒәйӘЁгӮ’еҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҹгҒҠеў“гҒ®ж’ӨеҺ»д»Ј
- д»ҸеЈҮгғ»дҪҚзүҢгҒ®ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгғ»еҮҰеҲҶд»Ј
- гҒ”йҒәйӘЁгҒ®еҖӢеҲҘе®үзҪ®жңҹй–“гҒ®е»¶й•·д»Ј
гҒ”йҒәйӘЁгӮ’еҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҹгҒҠеў“гҒ®ж’ӨеҺ»д»Ј
иҸ©жҸҗеҜәгҒ«гҒҠеў“гҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгҒҹгҒҢж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒҷгӮӢжөҒгӮҢгҒҜгҖҒгҒҠеў“гӮ’еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҹгҒҶгҒҲгҒ§гҖҒгҒ”йҒәйӘЁгӮ’ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒӘгҒӢгҒ«гҒҜгҖҒиҸ©жҸҗеҜәгҒ®гҒ”дҪҸиҒ·гҒ«зӣёи«ҮгҒ—гҒҰгҖҒгҒ”йҒәйӘЁгҒ гҒ‘гҒ гҒ—гҒҰж°ёд»ЈдҫӣйӨҠе…ҲгӮ’жҺўгҒ—гҒҰзҙҚйӘЁгҒҷгӮӢгҒӢгҒҹгҒҢгҒ„гӮүгҒЈгҒ—гӮғгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ”йҒәйӘЁгҒ гҒ‘гҒ гҒ—гҒҰгҒҠеў“гӮ’гҒқгҒ®гҒҫгҒҫгҒ«гҒҷгӮӢгҒЁж”ҫзҪ®еў“гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгғҲгғ©гғ–гғ«гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж”ҫзҪ®гҒ•гӮҢгҒҹгҒҠеў“гҒҜгҖҒдёҖе®ҡжңҹй–“гӮ’йҒҺгҒҺгӮӢгҒЁеў“ең°гҒ®з®ЎзҗҶиҖ…гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰж’ӨеҺ»гҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҠеў“гӮ’ж’ӨеҺ»гҒҷгӮӢгҒ®гҒ«гҒӢгҒӢгҒЈгҒҹиІ»з”ЁгӮ„гҖҒжңӘзҙҚгҒ®з®ЎзҗҶиІ»гҒҜи«ӢжұӮгҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҖҒиҰӘж—Ҹгғ»йҒәж—ҸгҒЁи©ұгҒ—еҗҲгҒЈгҒҰиЁҲз”»зҡ„гҒ«гҒҠеў“гӮ’ж’ӨеҺ»гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
д»ҸеЈҮгғ»дҪҚзүҢгҒ®ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгғ»еҮҰеҲҶд»Ј
иҸ©жҸҗеҜәгҒ®гҒҠеў“гҒ«зҪ®гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢеЎ”е©Ҷгғ»дҪҚзүҢгӮ„гҖҒиҮӘе®…гҒ«гҒӮгӮӢд»ҸеЈҮгҒҜгҖҒгҒқгҒ®гҒҫгҒҫж”ҫзҪ®гҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгӮ„еҮҰеҲҶгӮ’гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еЎ”е©ҶгӮ„дҪҚзүҢгҒ®ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®зӣёе ҙгҒҜ1дёҮеҶҶ~3дёҮеҶҶзЁӢеәҰгҒ§гҖҒиҸ©жҸҗеҜәгҒ®гҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҖҒеғ§дҫ¶зҙ№д»ӢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ§гӮҲгӮ“гҒ гҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«й јгӮҖгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
д»ҸеЈҮгҒҜгҖҒгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«йӯӮжҠңгҒҚгӮ’гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҹгҒӮгҒЁгҒ«гҖҒд»ҸеЈҮеҮҰеҲҶгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶжҘӯиҖ…гҒ«еӣһеҸҺгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒ®гҒҢгҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ”йҒәйӘЁгҒ®еҖӢеҲҘе®үзҪ®жңҹй–“гҒ®е»¶й•·д»Ј
еҖӢеҲҘе®үзҪ®еһӢгҒ®ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гҒҜеҖӢеҲҘгҒ«е®үзҪ®гҒ§гҒҚгӮӢжңҹй–“гҒ«еҲ¶йҷҗгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒжңҹй–“гӮ’йҒҺгҒҺгӮӢгҒЁгҒ”йҒәйӘЁгҒҜеҗҲзҘҖгҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҖӢеҲҘгҒ«е®үзҪ®гҒҷгӮӢжңҹй–“гӮ’延長гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиҝҪеҠ иІ»з”ЁгӮ’ж”Ҝжү•гҒҶеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ—гҒҹеҫҢгҒ®жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒ§гӮҲгҒҸгҒӮгӮӢиіӘе•Ҹ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ«гҒ—гҒҹеҫҢдҪ•еӣһеҝҢгҒҫгҒ§жі•иҰҒгҒҷгӮӢгҒ№гҒҚпјҹ
ең°еҹҹгӮ„еҖӢдәәгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘиҖғгҒҲж–№гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒдёғеӣһеҝҢгҖҒеҚҒдёүеӣһеҝҢгҒЁзҜҖзӣ®гҒ”гҒЁгҒ«гҖҒзҙ°гҒӢгҒҸжі•иҰҒгӮ’гҒҷгӮӢгҒӢгҒҹгӮӮгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдёүеӣһеҝҢгҒҫгҒ§гҒҠгҒ“гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒҹгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒ®гҒҠеёғж–ҪгҒҜгҒ„гҒҸгӮүпјҹ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠж–ҷгӮ„еҲ»еӯ—ж–ҷгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«йҮ‘йЎҚгҒҢжұәгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢ3дёҮеҶҶ~5дёҮеҶҶгӮ’гҒҠеҢ…гҒҝгҒ—гҒҰгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«жёЎгҒҷгҒӢгҒҹгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гҒ®гҒҠеҸӮгӮҠгҒ®д»•ж–№гҒҜпјҹ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®гҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒ®ж–№жі•гӮ„гғһгғҠгғјгҒҜгҖҒгҒ”йҒәйӘЁгӮ’е®үзҪ®гҒҷгӮӢе ҙжүҖ(йӣҶеҗҲе®үзҪ®еһӢгҒ®ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гҖҒеҖӢеҲҘе®үзҪ®еһӢгҒ®ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гҖҒжЁ№жңЁи‘¬гҖҒзҙҚйӘЁе Ӯ)гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒЎгҒҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
дҪҚзүҢгӮ„д»ҸеЈҮгҒҜж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ§гҒҚгӮӢпјҹ
еЎ”е©ҶгӮ„дҪҚзүҢгҒ®ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®зӣёе ҙгҒҜ1дёҮеҶҶ~3дёҮеҶҶзЁӢеәҰгҒ§гҖҒиҸ©жҸҗеҜәгҒ®гҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҖҒеғ§дҫ¶зҙ№д»ӢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ§гӮҲгӮ“гҒ гҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«й јгӮҖгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
д»ҸеЈҮгҒҜгҖҒгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«йӯӮжҠңгҒҚгӮ’гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҹгҒӮгҒЁгҒ«гҖҒд»ҸеЈҮеҮҰеҲҶгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶжҘӯиҖ…гҒ«еӣһеҸҺгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒ®гҒҢгҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ§гҒҷгҖӮ
жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒ®гҒҠеёғж–ҪгҒҜгҒ„гҒӨжёЎгҒҷпјҹ
гҒҠеёғж–ҪгӮ’жёЎгҒҷгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒҜгҖҒжі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒҢзөӮгӮҸгҒЈгҒҰдёҖдј‘гҒҝгҒ—гҒҹгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒ§гҒҠжёЎгҒ—гҒҷгӮӢгҒ®гҒҢгҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ§гҒҷгҖӮ
жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒҢзөӮгӮҸгҒЈгҒҹгҒӮгҒЁгҒ«гҒҠжёЎгҒ—гҒҷгӮӢгҒ®гҒҢгӮҖгҒҡгҒӢгҒ—гҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒжі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒ®гҒҫгҒҲгҒ«гҖҒгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«жҢЁжӢ¶гҒҷгӮӢгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒ§гҒҠжёЎгҒ—гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ§гӮӮеҲқзӣҶжі•иҰҒгҒҜгҒҠгҒ“гҒӘгҒҶгҒ№гҒҚпјҹ
гҒ”йҒәж—Ҹгғ»иҰӘж—Ҹгғ»ж•…дәәгҒ®з”ҹеүҚгҒ®еҸӢдәәзӯүж®ӢгҒ•гӮҢгҒҹдәәгҒҢжі•дәӢгғ»жі•иҰҒгӮ„гҒҠеў“еҸӮгӮҠгӮ’гҒҷгӮӢ(иҝҪе–„дҫӣйӨҠ)гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒж•…дәәгҒҢжҲҗд»ҸгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲж–№гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеҲқзӣҶ(ж–°зӣҶ)гӮ„жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶж„Ҹе‘ігҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ