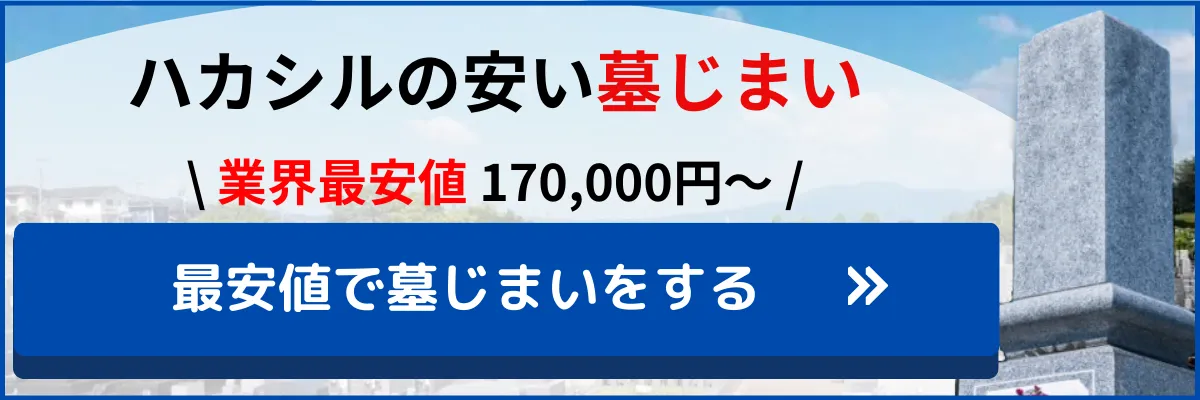葬儀費用・葬儀代の平均金額・相場や内訳と最安値でする方法
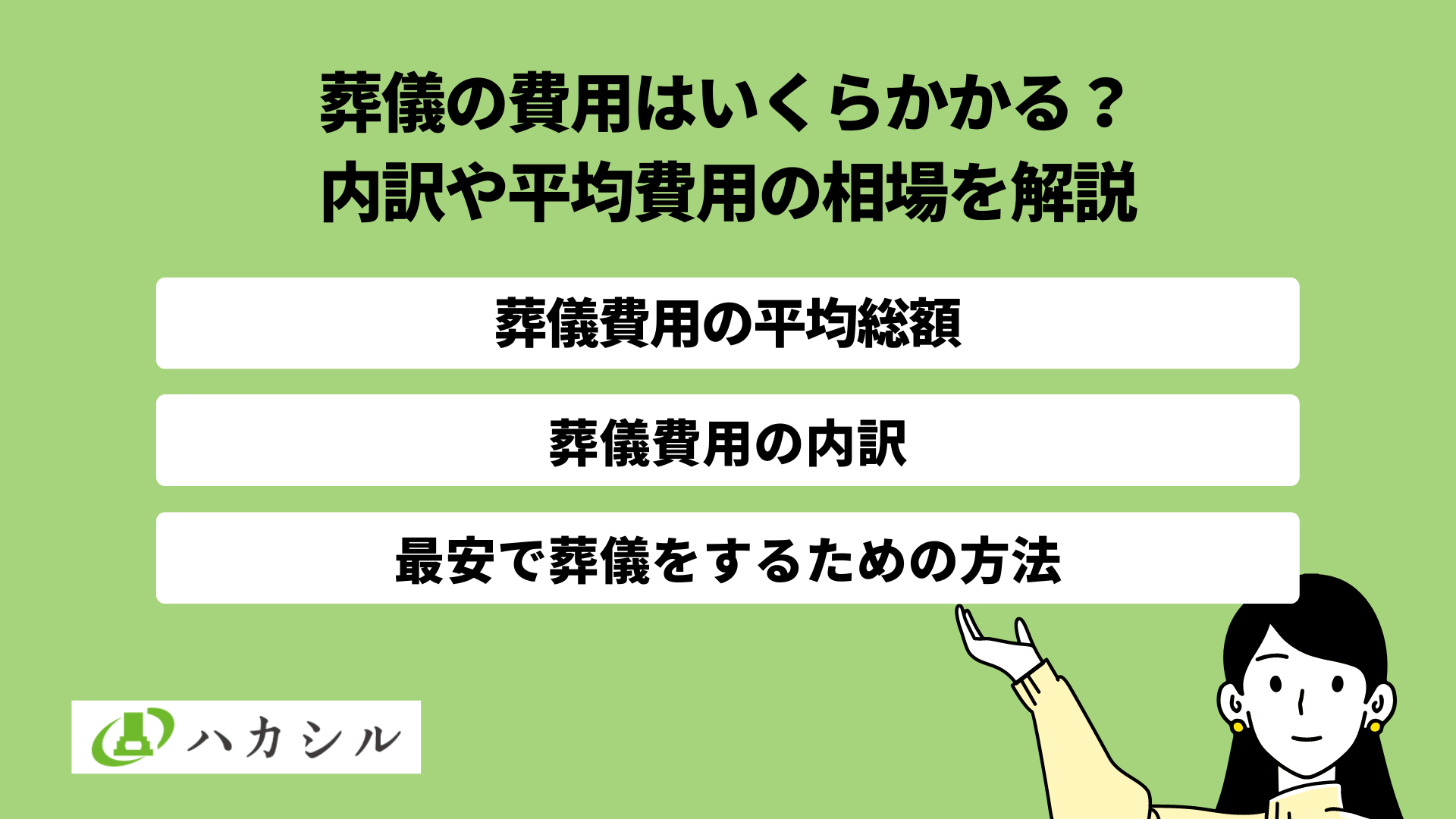
「葬式にいくらかかるの?」
「総額でいくら必要になるの?」
2022年の実際に葬式にかかった平均費用は、一般財団法人日本消費者協会の葬儀についてのアンケート調査報告書によると129.6万円程度です。
しかし、実際には130万円程度かかる葬式や20万円程度でできる葬式など料金に大きな幅があります。
どこにいくら費用がかかるのか内訳を知っておかなければ、平均費用以上の高額請求をされる可能性があるので注意しましょう。
- この記事で抑えるポイント
-
- 葬儀にかかる費用の内訳
- お坊さんに払うお布施相場
- 最安値で葬儀をする方法
もくじ(メニュー)
葬式(葬儀)にかかる平均費用は129.6万円程度
葬式の平均費用は10.5万円安くなっている
一般社団法人日本消費者協会によると、2016年の葬式にかかった平均費用は140.1万円でした。2021年の葬式にかかった平均費用は129.6万円で、10.5万円安くなったことが分かります。
平均費用の内訳の比較(目安)
| 項目 | 2016年8月~9月 | 2021年8月~12月 |
|---|---|---|
| 葬儀社に払う費用 | 121.4万円 | 111.9万円 |
| 参列者の接待費用 | 20.2万円 | 12.2万円 |
| お布施 | 37万円 | 42.5万円 |
| 香典返しにかかる費用※ | 38.5万円 | 37万円 |
| 支払い前合計金額 | 217.1万円 | 203.6万円 |
| 香典の金額 (差し引ける額) |
77万円 | 74万円 |
| 支払い合計金額 | 140.1万円 | 129.6万円 |
※香典金額の半額と仮定しています。
葬儀社や葬式のやり方で費用が変わる
葬式の平均費用は129.6万円ですが、全ての葬式が100万円台でおこなわれているわけではありません。安いもので15万円、高いもので200万円と葬式を依頼する葬儀社や葬式のやり方によって費用がおおきく変わります。
公営葬儀社と民営葬儀社で費用が変わる
| 公営の葬儀にかかる相場 | 民営の葬儀にかかる相場 |
|---|---|
| 15万円~82万円程度 | 20万円~136万円程度 |
公営の葬儀社とは、葬祭業連合会に加盟していて、さらに区民(市民)葬儀取扱指定店になっている葬儀社になります。
公営の葬儀社は、祭壇や棺の装飾を自分好みに変更することができませんが、葬式にかかる費用を安く抑えることができます。
民営の葬儀社とは、民間企業や寺院が運営している葬儀社になります。公営の葬儀社とくらべて祭壇や棺を自分好みにできたり、設備が充実した施設を使っていたりするため料金が高い傾向にあります。
葬式のやり方で費用が変わる
葬式は、通夜式を1日目におこなって2日目に告別式や火葬をおこなう二日葬、1日で告別式や火葬だけをおこなう一日葬、火葬だけをおこなう直葬の3つのやり方に分けられます。
二日葬・一日葬・直葬は、それぞれ葬式に呼ぶ人数によって、祭壇の飾り方や会食に用意する料理と香典返しの数が変わってくるため、葬式(葬儀)にかかる平均費用に差がでます。
葬儀社と葬儀のやり方別の費用目安
| 二日葬 | 一日葬 | 直葬 | |
|---|---|---|---|
| 公営 | 52万円 | 50万円 | 15万円 |
| 民営 | 136万円 | 82万円 | 21万円 |
葬式(葬儀)にかかる費用の内訳
葬儀社に払う費用の内訳
| 項目 | 平均費用(目安) |
|---|---|
| ご遺体の搬送 | 10㎞:1.5万円 |
| ご遺体の安置 (安置室代) |
3.5万円 (1日あたり) |
| 枕飾り | 2万円~3万円 |
| 布団 | 8,000円 |
| 仏衣(ぶつえ) | 1万円 |
| ドライアイス | 1万円 (1回あたり) |
| 湯灌(ゆかん) | 7万円 |
| 死化粧 (メイクアップ) |
4万円 |
| 棺 | 5万円~30万円 |
| スタッフ (人件費) |
3万円 (1人当たり) |
| 祭壇 | 5万円~200万円 |
| 装飾品 | 供花1.5万円~3万円 供物5,000円~2万円 遺影写真3万円~5万円 |
| 骨壺 | 8,000円~3万円 |
遺体の搬送
施設や病院から、自宅または葬儀社が管理している霊安室にご遺体を搬送する費用と葬儀会場(式場)から火葬場へ棺を搬送する費用は必ずかかります。
搬送代は移動距離で料金が決められます。
10㎞あたりの平均相場は1.5万円程度になります。
ご遺体の安置
病院や施設で亡くなられたときは、自宅か葬儀社で運営している安置室(霊安室)にご遺体を安置する必要があります。自宅にご遺体を安置できれば安置室代はかかりません。しかし、葬儀社で運営している安置室に運ぶ場合は、安置室代がかかります。
安置室代の平均費用は1日あたり3.5万円程度です。
枕飾り
仏教では亡くなったご遺体のそばに、枕飾りといって、ろうそくや線香を置く習慣があります。神道は宗教がちがうので用意するものが変わります。また、キリスト教では枕飾りを使用しません。
家に仏具があって枕飾りをレンタルする必要がないときや宗教の考え方から枕飾りを使用しないときは費用がかかりません。
葬儀社に枕飾りを一式レンタルするときの平均費用は2万円~3万円程度です。
布団
納棺するまでの間はご遺体を安置するための布団が必要になります。布団は故人が使っていたものでかまいません。葬儀社に専用の布団を用意してもらうときの平均費用は8,000円程度です。
仏衣(ぶつえ)
仏衣(ぶつえ)とは亡くなった人が着る白い着物です。仏教と神道は共通して死装束(しにしょうぞく)とも呼びます。
キリスト教には仏衣のような決まった服装がありません。
仏衣は必ず着させなくてはいけないというルールはなく、故人が生前に愛用していた服を着させることもできます。仏衣を用意してもらうときの平均費用は1万円程度です。
ドライアイス
ご遺体は冷却しておかないと腐敗して体液が外にもれたり、腐敗臭が発生します。故人の体の大きさや季節によってドライアイスの使用量や交換回数が変わります。
ご遺体を火葬するまでの間はドライアイスが必要で、1日1回程度ドライアイスを交換しなければなりません。ドライアイス1回分の平均費用は1万円程度です。
湯灌(ゆかん)
湯灌(ゆかん)はご遺体をお風呂に入れ、爪を切ったり、顔そりをするといった行為です。湯灌と合わせて死化粧(しにげしょう)をしてくれる葬儀社もありますが、死化粧が別料金になる葬儀社もあります。湯灌にかかる平均費用は7万円程度です。
死化粧(しにげしょう)
死化粧はご遺体の最期の姿を綺麗に整えたり、闘病の跡や傷口を隠したりする行為です。ご遺体の状態がよければ死化粧をする必要がなく費用がかかりません。
死化粧にかかる平均費用は4万円程度です。
棺(ひつぎ)
棺はご遺体を収納する箱です。
棺がなければご遺体を火葬することはできません。棺は柄やかざりによって費用が変わります。安い棺は5万円程度ですが、柄やかざりにこだわると30万円程度になります。
祭壇
亡くなった方や神様へ供物(くもつ)をささげる台を祭壇といいます。
お寺を連想させる宮造りの白木祭壇や台の上に生花で華やかに飾り付ける生花祭壇、宮造りではないシンプルな形をしているモダン祭壇、現代祭壇があります。
サイズや装飾(花の種類や数、思い出の品の展示など)により費用は変動しますが、5万円~200万円程度します。直葬では原則的に祭壇を使わないため、費用はかかりません。
供花(くげ)・供物(くもつ)
供花・供物は祭壇の左右に飾る生花と果物が盛り付けられた籠(かご)で、差出人の名前を名札に記して飾ります。供花の平均費用は1.5万円~3万円程度で、供物の平均費用は5,000円~2万円程度です。
供花・供物は親族だけでなく、友人や会社関係者から頂くことがあります。原則的にお礼の品を用意する必要はありませんが、マナーとしてお礼状を出す必要があります。
遺影写真
遺影写真は祭壇に飾る故人の写真になります。
遺影写真を生前に準備していないときは葬儀社に故人が映っている写真や写真データを渡して加工してもらう必要があります。
遺影写真を依頼するときの平均費用は3万円~5万円程度ですが、自分で写真と額縁を用意すれば5,000円程度で用意することが可能です。
骨壺
骨壺は火葬した後の骨を収納する容器です。
骨壺は安いもので8,000円程度ですが、柄や材質によっては数万円~数十万円になることも珍しくありません。
葬儀社のスタッフ
葬儀社のスタッフはご遺体や棺の搬送、納棺、葬儀全体の段取りや当日の司会進行、受付のお手伝いなどをおこなってくれます。参列者が多いときは、葬儀社のスタッフを追加で用意してもらうことになり、葬式費用が高くなります。
スタッフを追加しなくてはいけないときの平均費用は1人あたり3万円程度です。
参列者に払う費用の内訳
| 項目 | 平均費用(目安) |
|---|---|
| 通夜振る舞い | 3,000円~7,000円 (1人あたり) |
| 精進落とし | 5,000円~8,500円 |
| 香典返し | 2500円 (1つあたり) |
| 会葬礼状 | 3,000円~5,000円 |
香典返し
香典返しは参列者に頂く香典のお返しの品になります。
香典返しは頂いた香典の半分もしくは3分の1程度のものを返すのがマナーです。参列者が渡す香典の相場は、友人や会社関係者といった知人、親しくない親族は5,000円~1万円で、親しい人や親族は3万円~10万円程度になります。
参列予定者が多く、葬式が終わった後に香典返しを個別に贈るのがむずかしいときは2,500円~5,000円程度の品を用意して、参列して頂いた日にお返ししてしまうのが良いです。高額の香典を頂いた方には後日、金額に見合った香典返しの品を贈ると良いです。
会葬礼状
会葬礼状とは通夜式や葬儀式、告別式に参列して頂いた方への感謝を伝えるお礼状です。
参列者が少なければ自分で用意してしまっても問題ありません。
参列者数が多いと印刷の発注と受け取りまでを自分でおこなう必要があるので大変です。葬儀社の多くは50枚で1セットとして平均費用3,000円~5,000円で用意してくれます。
通夜振る舞い
通夜振る舞いとは通夜式をした後に、参列者とお坊さんを呼んでおこなう会食です。神道は直会という呼び方になり、キリスト教には会食をする習慣がありません。
通夜式に呼ぶ人数によって用意する料理の数が変わりますが、通夜振る舞いにかかる平均費用は1食あたり7,000円程度です。
現代においては感染症対策のため会食(通夜振る舞い)をおこなわないことが増えています。通夜振る舞いをしないときはカタログギフトやお弁当を用意して参列者に持ち帰ってもらいます。
カタログギフトやお弁当にかかる平均費用は1人あたり1,000円〜5,000円程度です。
精進落とし
精進落としとは火葬式や初七日法要をした後に参列者とお坊さんを呼んでおこなう会食になります。通夜振る舞いとおなじように参列者に感謝を伝える場です。
神道は直会という呼び方になり、キリスト教には会食をする習慣がありません。
通夜振る舞いよりも豪華な料理がならぶことが多いため、精進落としにかかる平均費用は1食あたり5,000円~8,500円程度です。
通夜振る舞いとおなじく、感染症対策のため精進落としをおこなわず、カタログギフトやお弁当を用意して参列者に持ち帰ってもらうことが増えています。
カタログギフトやお弁当にかかる平均費用は1人あたり1,000円〜5,000円です。
お坊さんに払う費用(お布施)
お葬式に渡すお布施の全国平均
お布施とはお坊さんに読経をしてもらったり、戒名をつけてもらったお礼として渡す金銭です。お坊さんを呼んだ時の交通費や食事代も含まれます。
神道ではお布施を玉串料、キリスト教では献金と呼びます。戒名をつけるのは仏教のみです。
一日葬はお坊さんや神主、牧師が1日しか来ないのでお布施(玉串量や献金)の相場は10万円~30万円程度、二日葬は2日間にわたってお坊さんや神主、牧師が来るため、20万円~50万円程度になります。
故人につけた戒名のランクが高ければお布施の金額がさらに上乗せされます。
地域別のお布施の平均費用
| 地域 | 平均費用(目安) |
|---|---|
| 北海道 | 25.4万円 |
| 東北 | 34.2万円 |
| 関東(東京以外) | 48.7万円 |
| 関東(東京) | 57.2万円 |
| 北陸 | 31.6万円 |
| 東海 | 43.6万円 |
| 近畿 | 38.7万円 |
| 中国四国 | 43.7万円 |
| 九州 | 35万円 |
| 布施の平均 | 42.5万円 |
※第12回 葬儀に関するアンケート調査報告書より
直葬では原則的にお坊さんや神主、牧師を呼ばないため、お布施(玉串量や献金)の必要はありません。
戒名にかかるお布施の平均費用
戒名とは亡くなった人が仏の世界における名前になります。
戒名にはランクがあり、安いものは5万円、高いもので100万円以上します。戒名料は読経料に上乗せされてお布施として渡します。
戒名は絶対につけなくてはいけないものではありませんが、戒名をつけなかったことでお墓に納骨をするときに、お坊さんに拒否されるトラブルが発生する可能性があります。
戒名のランクと平均費用
| 項目 | 平均費用 |
|---|---|
| 信士・信女 | 5万円~30万円 |
| 居士・大姉 | 40万円~80万円 |
| 院信士・院信女 | 50万円~200万円 |
| 院居士・院大姉 | 100万円以上 |
葬儀施設(式場や火葬場)に払う費用の内訳
| 項目 | 平均費用(目安) |
|---|---|
| 式場使用料 | 5万円~30万円 |
| 火葬料 | 7.5万円 (東京23区) |
式場使用料
葬儀社と式場は運営する会社がおなじ場合もあれば、葬儀社と式場が別の会社である場合もあります。式場が別の会社のときは式場使用料が必ずかかります。
葬儀社と式場の運営会社がおなじ場合は、式場使用料が発生しないことがあります。
公共の式場を使用できる場合、かかる平均費用は5万円程度ですが、民間で運営している式場は高いところで30万円程度かかります。
火葬料
ご遺体を火葬する費用は自治体によって大きくちがいます。東京(23区)では7.5万円の費用がかかりますが、他の地域では0円~5万円程度で火葬することができます。
火葬料は季節や原料・燃料費の高騰によって燃料費特別付加火葬料という追加費用が発生することがあります。
地域別火葬料の目安
| 地域 | 火葬料の目安 |
|---|---|
| 北海道・東北 | 0円~4.9万円 |
| 関東 (東京・神奈川県横浜市以外) |
0円~1万円 |
| 東京23区内 | 7.5万円 |
| 東京23区外 | 5.96万円 |
| 神奈川県横浜市 | 5万円 |
| 中部・甲信越 | 0円~1.5万円 |
| 関西 | 1万円~2万円 |
| 中国・四国 | 8,200円~2.5万円 |
| 九州・沖縄 | 5,000円~2.5万円 |
葬式(葬儀)を最安値でする方法
葬儀社の割引サービスを利用する
ほとんどの葬儀社は会員になる、事前申し込みをする、資料請求をするといったことをしてくれた人に対して割引をおこなっています(直葬は対象外がほとんど)。
割引サービスは併用できないことがほとんどです。また、誰もが同じ割引サービスを受けられるとは限らないので、自分が利用できる割引サービスを選ぶ必要があります。
| 項目 | 平均割引額 |
|---|---|
| 事前申込 (30日前申込が必須) |
6.9万円~10.9万円 |
| 資料請求 | 5.6万円 |
| 会員になる | 5.3万円~6.7万円 |
存命中に最安値で葬式を計画するなら事前申し込み
事前申し込みとは生前予約を意味します。事前申し込みの適用は最低でも30日は存命していないといけません。ほとんどの葬儀社は事前申し込みから2年経つと割引額が上限に到達します。他の割引サービスとの適用はできませんが、割引額が最も高いです。
葬儀社選びの日程に余裕があるときは資料請求する
ご家族が危篤の状態で葬儀社をそろそろ決めなくてはいけない、といったときは資料請求をしておくとよいです。資料請求をしておくと会員にならなくても5万円~6万円程度の割引サービスを受けることができます。
資料請求をしていないときは会員になる
会員になることによって受けられる割引サービスは、事前申し込みや資料請求といったことが必要ないため、すぐに葬儀社を決めなくてはいけない場面でも利用することができます。
年会費を求められることはほとんどありませんが、入会金が3,000円~1万円程度かかる場合があります。入会金がかかっても生前予約の次に割引額が高いです。
葬祭費補助金制度を利用する
葬祭費補助金制度とは、故人の葬式や埋葬をおこなった人に支給される給付金制度です。条件としては亡くなった方もしくは葬式をおこなった人が国民健康保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療保険のいずれかに加入している必要があります。
葬式が終わった後に自治体の窓口で手続きをおこなうと最大で7万円の給付金を受け取ることができます。
公務員共済組合の給付金を利用する
公務員共済組合の給付金とは、故人が地方公務員や教員だったときに加入していた共済組合から葬祭費として受け取れる給付金です。
国家公務員であれば、国家公務員が加入する共済組合から葬祭費として給付金を受け取ることができます。
地方公務員が受け取れる葬祭費は最大で5万円、国家公務員が受け取れる葬祭費は最大で27万円になります。
おもてなしの料理を自分で用意する
通夜振る舞いや精進落としといった出席者をおもてなしする料理を葬儀社にお願いすると1食あたり5,000円~7,000円になることがあります。それぞれの会食する場所や料理は自分で予約したり、手配したりすれば1食あたり3,000円程度に抑えることが可能です。
最近では感染症対策のために会食をせず、カタログギフトを渡すことも珍しくありません。カタログギフトなら1人あたり2,500円~5,000円程度に抑えることができます。
お坊さん手配サービスを利用する
現在はお坊さんを手配するサービスがあります。
お坊さん手配サービスを利用すれば、読経と戒名をつけることに対して高額な費用を払う必要がなくなります。お坊さん手配サービスの費用は10万円程度です。
ただし、お坊さん手配サービスを利用するときは、事前に先祖が眠るお墓を管理している菩提寺と相談して決める必要があります。菩提寺ともめてしまうと納骨させてもらえない、葬式が終わった後に法要をしてくれないといったトラブルに発展する場合があります。
最安値でおこなったときの葬式(葬儀)費用目安
二日葬を最安値でおこなった時の費用目安
| 生前葬 | 会員登録 | 資料請求 | |
|---|---|---|---|
| 二日葬 (最安平均) |
65万円 | 65万円 | 65万円 |
| 香典返し (20名分) |
5万円 | 5万円 | 5万円 |
| 料理 (20名分) |
5万円 | 5万円 | 5万円 |
| 火葬料 | 7.8万円 | 7.8万円 | 7.8万円 |
| 手配 サービス |
10万円 | 10万円 | 10万円 |
| 値引額 | -10万円 | -6.7万円 | -5.6万円 |
| 補助金 | -7万円 | -7万円 | -7万円 |
| 香典 (20人) |
-10万円 | -10万円 | -10万円 |
| 合計費用 | 56.8万円 | 59.1万円 | 60.2万円 |
二日葬を最安値でおこなった時の費用目安です。
合計費用で見れば生前葬が1番お得ですが、事前申し込みをして、依頼者が亡くなる前に葬儀社がつぶれてしまったらお金が戻ってこないリスクがあります。
リスクを考えると、葬儀社を決めるときに会員になって割引をする、もしくは資料請求をして割引する方がよいでしょう。
香典返しは1人あたり2,500円のカタログギフトと仮定していますが、呼ぶ人の関係性によっては5,000円のカタログギフトにするなどランクの変更をすることをおすすめします。
オプションを多くつけたり、ランクを上げると、最安値で葬式をおこなうどころか、想定よりも高くなってしまうことがあります。ハカシルでは葬式の選び方やお見積り手配といったサポートをおこなっているのでお気軽にお問い合わせください。
一日葬を最安値でおこなった時の費用目安
| 生前葬 | 会員登録 | 資料請求 | |
|---|---|---|---|
| 一日葬 (最安平均) |
35万円 | 35万円 | 35万円 |
| 香典返し (20名分) |
5万円 | 5万円 | 5万円 |
| 料理 (20名分) |
5万円 | 5万円 | 5万円 |
| 火葬料 | 7.8万円 | 7.8万円 | 7.8万円 |
| 手配 サービス |
10万円 | 10万円 | 10万円 |
| 値引額 | -7.5万円 | -5.3万円 | -5.6万円 |
| 補助金 | -7万円 | -7万円 | -7万円 |
| 香典 (20人) |
-10万円 | -10万円 | -10万円 |
| 合計金額 | 38.3万円 | 40.5万円 | 40.2万円 |
一日葬を最安値でおこなったときの費用目安です。
会員になったときの割引より、資料請求したときの割引を適用したほうが安くおさえることができる可能性が高いです。
香典返しは1人あたり2,500円のカタログギフトと仮定していますが、呼ぶ人の関係性によっては5,000円のカタログギフトにするなどランクの変更をした方が良いです。
直葬を最安値でおこなったときの費用目安
| 民間の葬儀社 | |
|---|---|
| 直葬 (最安平均) |
9万円 |
| 火葬料 | 7.8万円 |
| 補助金 | -7万円 |
| 合計金額 | 9.8万円 |
直葬を最安値でおこなったときの費用目安です。
ほとんどの葬儀社では、直葬を割引対象としていません。仏具やお坊さんを呼ぶときはさらに倍以上の金額がかかることがあります。
また、自治体によっては直葬は補助金の対象としているところもあります。直葬を選ぶ前に自分の住んでいる自治体では直葬が補助金の対象かを確認する必要があります。
公営の葬儀社を利用するために区民(市民)葬儀利用券を発行する
区民(市民)葬儀利用券は公営の葬儀社を利用するためのチケットのようなものです。
家族の誰かが亡くなったら最寄りの役所に行き、区民(市民)葬儀利用券の交付申請書を提出することで区民(市民)葬儀利用券をもらうことができます。
区民(市民)葬儀利用券をもらったら、自治体に紹介された葬儀社に連絡し、区民(市民)葬儀利用券を渡して葬式をおこなうことを伝えましょう。
区民(市民)葬は祭壇や棺の装飾にこだわることはできません。
区民(市民)葬でおこなったときの費用目安
| 二日葬 | 一日葬 | 直葬 | |
|---|---|---|---|
| 葬式に かかる費用 |
25.5万円 | 24.5万円 | 9万円 |
| 香典返し (20名分) |
5万円 | 5万円 | – |
| 料理 (20名分) |
5万円 | 5万円 | – |
| 火葬料 | 6万円 | 6万円 | 6万円 |
| 手配 サービス |
10万円 | 10万円 | – |
| 補助金 | -7万円 | -7万円 | -7万円 |
| 香典 (20人) |
-10万円 | -10万円 | - |
| 合計金額 | 34.5万円 | 33.5万円 | 8万円 |
葬儀(葬式)の費用でよくある質問
葬儀に呼んだお坊さんにいくら包む?
葬儀にお坊さんを呼んだときはお布施を渡さなくてはいけません。お布施とは読経をしてもらったり、戒名をつけてもらったお礼として渡す金銭です。地域によって包む金額が大きくちがい、最大で20万円の差になることがあります。
家族葬は全部でいくらかかる?
家族葬の費用は50万円~130万円程度になります。葬式に呼ぶ参列者数によって香典返しの品や食事の準備をする量が変わるため、費用も大きく変わります。
葬儀の費用は誰が払う?
葬儀の費用は、原則的に喪主が支払うことがほとんどです。本来は葬儀の手配や段取りをおこなう施主が支払いますが、喪主が施主の役割をつとめることがほとんどなので、葬儀の費用を払う人は喪主ということになります。家庭によっては残った遺族で負担し合うことも珍しくありません。
戒名料は必要?戒名がないとどうなる?
戒名をつけるのは仏教徒だけです。他の宗教を信仰している、無宗教である場合は必要ありません。しかし、先祖のお墓を管理している菩提寺がある場合は、戒名をつけるかつけないかを相談して決める必要があります。菩提寺に相談せずに戒名をつけないでいると納骨を拒否される可能性があります。